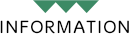[ようこそ、信州へ #011]金子 雅和さん(映画監督)&大林 千茱萸さん(映画家)

金子雅和(右)と大林千茱萸
信州発 世界へ
須坂ロケの映画「アルビノの木」
4月14日から都内で金子雅和監督特集上映
須坂市をメインロケ地として撮影した映画「アルビノの木」は、海外の映画祭で10冠を達成し、今月も出品されたスペインの映画祭で観客賞を受賞して注目を集める。県内では、木曽地方で6月に開催されるアートフェスティバル「木曽ペインティングス」で上映が決まっている。監督した金子雅和さんは、初長編「すみれ人形」が毎年秋に開催される「うえだ城下町映画祭」の自主制作映画コンテストで審査員賞を受賞するなど、信州とも縁が深い。4月14日から都内の映画館で特集上映が始まるのを前に、うえだ城下町映画祭自主制作映画コンテストで金子さんを見出した大林千茱萸さんと語ってもらった。
上田市で毎年秋に開催される「うえだ城下町映画祭」では、2003年から自主制作映画コンテストが始まった。大林千茱萸さんは初回から審査員を務める。金子雅和さんは2007年、第5回コンテストに映画美学校の修了制作で手掛けた「すみれ人形」を応募し、審査員賞に当たる大林千茱萸賞を受賞した。「すみれ人形」は、失踪した妹をめぐって腹話術師の兄と、幼なじみの樹木医の男がたどる異形の愛の物語。金子さんはこの受賞などをきっかけに、2008年劇場デビューした。それから10年。人間がどう生きるかを自然との関係の中で浮き彫りにした「アルビノの木」まで、現代を舞台に普遍的なテーマを探る作風が貫かれている。

「アルビノの木」©kinoe
大林 コンテストへの応募は、年によって差はありますが約140作品。立ち上げたころ、世間では上映時間は5分以内といった短編を扱う映画祭が流行っていました。長編を受け付ける映画祭がなかった。うえだ城下町映画祭自主制作映画コンテストの第1回目も、蓋を開けたらいわゆる「ショートショートフィルムフェスティバル」に代表されるような短編映画祭と差がなくて。戦前から映画撮影が盛んな上田市側から「映画のまち」にしたい、若手を育てたいと求められていたこともあり、「15分以上無制限」という中編、長編を受け付けることを特徴にすることが、未来の作家が育つ土壌になるのではと提案しました。
審査で見る時、どれほど長い作品が来ても「全作品、絶対に早回しはしない」「応募作は全作品観る」と約束事を自分自身に課しました。映画のつくり方と観る方の両方に携わって来た私の「役割」は、責任と覚悟を持って1本の作品に向き合うことだと考えています。審査員3人の中で、私は“発掘系”。世の中にはまだ出ていないけど、作家性や視点があるオリジナルな世界を持つ作品に賞を贈ります。自分の好き嫌いという「好み」で判断することは避け、観た後にざらっとした何か手触りが残った作品を選ぶことは一貫していて、スクリーンの向こう側に意思を持って一つのものをつくることが感じられ、この先も作品を撮り続けてくれる気配を感じる作家さんを選んでいます。
「すみれ人形」と出合った第5回までは、キャメラを手持ちして気分や雰囲気を撮影する偶然狙いの作品が多かった。金子さんの作品は、三脚を使ってキャメラを据え、作家の視点や世界をつくり出していた。物語が猟奇的でだめとか、エログロという人もいたけれど、それを超えて訴える確固たるものがありました。画面の中もしっかりつくられていたけれど、切り取られた画面を包み込む外側に作家の意思…次にどんなことを映画でしたいのかを強く感じました。
金子 映画美学校の修了制作は、選ばれた人が助成を受けて、ほかの人がスタッフをやる仕組みです。とにかく撮りたかったから内容も突出していた部分はありますが、インディーズ映画では自分たちの身の回りの話を、生活実感をもって描く題材がわりと多かったことに反発があって、そういうものを面白いと思わなかったんです。
自分にとっての映画とは、良い意味でのフィクション。構築された寓話を見せることで、逆に現実の何かを感じさせるような、生きている手応えを描きたい、という思いが強くありました。

「すみれ人形」ⓒ映画美学校

「鏡の娘」ⓒkinone
大林 実際に、映っているもの自体は人間をはじめリアルだけど、物語や背景からはリアルでないものが炙り出てくる。その異世界を描くことで、逆に本当のことも見えてくるという「入れ子構造」を金子さんの作品からはいつも感じます。リアルなものをリアルなまま見せることほど映画から遠いものはない。「すみれ人形」は人の体を切ったり、燃やしたりすることが具象としては出てくるけれど、それがエログロナンセンスに転ばないのは、ものごとの根っこがエログロを飛び越えた先にある想像力の広がり、普遍性につながっているからだと思っています。
初めて作品を観た時から、金子さんの作家性はぶれていません。グリム童話「ラプンツェル」を題材にした母娘の物語「鏡の娘」(2009年、うえだ城下町映画祭自主制作映画コンテスト審査員賞受賞)も、神隠しを扱った「逢瀬」(2013年、同コンテスト大賞受賞)も、一見クラシックなつくりのようでいて、実はとても現代的な“今”の映画になっていた。作品を観るたびに、枝葉としてのテクニック、予算、物語の広がりはあるけれども、毎回、作品を通じて信念や映画づくりの姿勢がわかる。信じてよかったと思う監督です。

「すみれ人形」で2007年の自主映画制作コンテストで審査員賞を受賞した金子雅和さんⓒうえだ城下町映画祭
境界線を越える象徴としての水 普遍的な物語が評価
「映画は対話」 自分を投影できる豊かな余白
「アルビノの木」は、農作物を荒らす害獣駆除に従事する青年が主人公。母親の手術費用を用立てるため、ある山里では特別な存在として崇められてきた白鹿を撃ちに行く。文明の対立といった国境や時代を超えても通じる問題が浮かび上がる。

金子 大林さんに「アルビノの木」を観ていただいたのは2年ほど前、公開の時ですね。
大林 「アルビノの木」は全体が、それまでの作品で描かれてきたモチーフのハーモニーになっていて、映画をつくり上げるスケールが大きくなった印象を受けました。
金子 2008年に「すみれ人形」が劇場公開されて、その年の夏ごろには「アルビノの木」を撮ろうと決めていました。最終的に変わった部分もありますが、白鹿と猟師の話という軸は当時から考えていました。ただ、お金など諸条件でなかなか実現できず、経験不足も感じていたので。「すみれ人形」は63分だけど、テーマが映画5本分あるようだと言われたほど、ひとつひとつのシーンが突出してしまっていました。長編映画を撮るために、演出や編集、ストーリーテリングの技術・経験を上げ、人脈を広げたいと、5年間で短編を6本撮りました。
金子さんが監督する作品には、水辺の風景が欠かせない。
「アルビノの木」では主人公がヒロインと水辺で出会い、白鹿を追い掛けて川の中を歩いて行く姿が物語の鍵になっている。
金子 実家は東京なのですが、町の中の噴水とか、水が流れるのを見るのが好きな子どもでした。水の中を歩いたり、水に浸かったりした時に、人間と人間以外のものの境界線がちょっと曖昧になっていく感触があると思うんです。僕の映画の中で物語が大きく展開していく、主人公が何かを超えていくポイントになるのは、水の中に入っていく時なんです。
大林 金子作品には全体を通して「自然」がキーワードとして出てきます。でも、本来自然は、映画で切り取った瞬間に不自然になる。ことに水は、人間がコントロールできないものです。木や影、陽の光は、照明部や美術部、CGなどの技術で補えても水は一番監督が御しにくい難しさがある。金子監督はロケーションを含め作品で自然を追い求めていながら、「不自然なもの=映画」と対峙しつつ、「自分の映画」を追い求めているように見受けられる。
キャメラを据えることは、映画人にとって「世界をそこにつくる」ということ。自然さと不自然さのせめぎ合いの境界線に水を据えることで、その揺らめきを、見る側は象徴として感じます。つくり手が100%制御できない象徴としての水には、見る人の心も映り、記憶に残る装置としても成立している。観る側にとって「映画は対話」でもあるので、作家が御さずに残した、その数パーセントに自分を入れ込んでいくことも映画を観る密かな楽しみ。映画の残り香を心に積み重ねることで、自分の中に映画が根付いてゆく。そういう意味でも金子監督の作品は、心に根付く映画です。
金子 自分たちを超えたもの、制御できないものに憧れがあったり面白いと思ったりするんです。一方、映画をつくることは制御していくことでもあり、その闘いの中で、ものづくりをしていくことに魅力を感じます。
「アルビノの木」は2016年の公開後、ポルトガルの映画祭「フィゲイラ・フィルム・アート」でグランプリ、台湾の「フォルモサ台湾国際映画賞」で最優秀アジア映画賞に輝くなど、海外映画祭で10冠に輝いた。水辺のウェットな風景、日本だけにとどまらない普遍的な物語性などが高く評価される。
金子 「日本にもこういうところがあるんだ」と、風景描写に驚く反応は各国共通していました。「アルビノの木」で映した、たゆたうような日本的な水の感じが、海外の人には魅力に感じるようです。さらに欧州では、ある都会の人には切り捨てるべきものが、違うエリアの人には守るべきものだという「文化の対立による葛藤」を受け入れてもらった印象です。映画は日本国内の話だけれど、万国共通のテーマを感じ取ってもらえたと思います。
大林 バブル時代以降ここ数10年、日本映画は海外マーケットでは、漫画の原作ばかり、物語にオリジナル性がない、子どものための映画、テレビ資本での製作というのが定着して買い手が離れています。そのような状況下だからこそ「アルビノの木」は、世界の共通言語としての日本映画として受け入れられたのだと思います。
グローバリズムをつくっているのはローカリズム。日本の、誰も知らない山奥の町でさえ、文化の対立が起こっている。映像に映っているのは自分の国とは明らかに違う文化だけれども共感でき、時と国を超えた死生観にも普遍性がある。それが映画として、風景も含めて、興味深く受け入れられているのではないかと思います。私がそうだったように、ざわざわしたものを体に残されて考えさせられる映画だろうなと。映画はいすに座ったまま時空を超え、心の旅に出られることが醍醐味。「アルビノの木」は、海外の観客に、日本を旅する心の窓を開ける力を持っている映画だと思います。