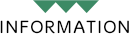[聞く/entre+voir #008] 佐藤壮生さん (信濃大町あさひAIR)〜大町が芸術の街になる①

信濃大町あさひAIR 佐藤壮生さん
今やりたいことは、アーティストの切実さを応援すること
そして、地域の切実な人たちと出会い
社会構造の中でテーマや場を設定していきたい。
2017年夏、「北アルプス国際芸術祭2017 ~信濃大町 食とアートの廻廊~」が 、大町市で開催される。総合ディレクターには「越後妻有 大地の芸術祭の里」「瀬戸内国際芸術祭」を手がけた北川フラム氏。土地固有の生活文化を表現する「食」と、地域の魅力を再発見する「アート」の力によって、北アルプス山麓の地域資源を世界へ発信することを目指すという。そこで大町のアートを支えるキーマンを追いかけていこうと思う。
トップバッターとして、アーティスト・イン・レジデンス(AIR)プログラムを中心とした地域の芸術活動発信拠点構築事業「信濃大町あさひAIR」でコーディネーターを務める佐藤壮生さんに聞いた。AIRとは、招聘されたアーティストが、ある土地に滞在し、作品の制作やリサーチ活動を行なうこと、またそれらの活動を支援する制度を指す。
さまざまな同時代性が多様に存在していることを受け入れるきっかけに。
◉まず、佐藤さんが大町でかかわってきた芸術活動について教えていただけますか?
大町には、2012年に安曇野に引っ越してきてから関わり始めました。最初は鳥獣被害対策員としてサルを追いかけていて、そのうち「信濃の国 原始感覚美術祭」でアートディレクターをしている杉原信幸さんを紹介してもらったんです。「原始感覚美術祭」には最初の年は遊びにいっただけでしたが、2013年は作家として参加し、コーディネーターをやらせてもらいました。僕は「忘れてないけど、思い出せない」というテーマで土を素材に作品制作をしていたのもあって、原始感覚と親和性が高いんです。その後、ガイドツアーやイベントを企画する「ぐるったネットワーク大町」が大町ラボラトリという講座に北川フラムさんをお呼びして、その流れが2014年の「信濃大町 食とアートの廻廊」という芸術祭につながります。僕としては小間使いとして手伝うくらいに思っていたら相応の責任者になっていて(苦笑)。その経験から、もし次にやるときは自分が責任をもってやろうと思い、2015年はたくさん企画書を書いたんです。そのひとつが大町のレジデンス事業につながりました。
考えてみると、この4年間、さまざまな形でアートの運営に関わらせてもらっています。個人の強い意志で行われている「原始感覚美術祭」、地域のNPO法人による「信濃大町 食とアートの廻廊」、そして市が文化行政として行う「北アルプス国際芸術祭」と、異なる趣旨で運営されている3つの芸術祭に関わることになりました。そのほかにも、麻倉で「つくること」自体の楽しもうとアンデパンダンのような活動に関わらせてもらったり、あさひAIRで国内外の作家さんをサポートしたり、すごく贅沢な経験をさせてもらっています。
◉AIRについては、長野県でもポツポツ動きが出てきました。佐藤さんがAIRに可能性を感じたのはなぜですか?
状況的に見ると、アーティスト・イン・レジデンスは芸術振興と国際交流を大きな目標にしていると思います。個人的には、とにかく自分で考えて行動する面白い人を大町に呼べるというのが、可能性を感じた部分です。自分自身に向かい合って、背中で人生を語れる大人がちゃんと注目されたらいいなと。アーティストって、わからない人からすれば、本当に謎な人たちなのだと思います。一見、生活の役に立たないことに一生懸命になっている。でも、こういうふうに「つくること」へ本気で向かい合って生きている人が、世界中に「いる」と地域で認知されるのが面白い。
先日、大町の中学校のキャリア教育の授業で、グローバリズムと第二次産業革命の話をしました。今の時代、世界中の国々が分業して現代生活を支えているということ。そして、その仕事の多くはみんなが気がつかないうちに、コンピューターに移行しつつある。そうやって労働の形が抜本的に変化しつつあるということを、あまり自覚せずに暮らしているように思うんです。
例えば、僕のカミさんは、子供のころの夢が郵便局でハガキを分ける仕事だったんです。だけど、その仕事はコンピューターに取られてしまった。過去20年はそういうことが頻繁に起こったし、これからの20年はもっと起こる。そうなったときに、今の日本で大人になるプロセスはけっこう危ういと思っていて、社会への従順さより、創造性が個人として生き残るために必要な時代だと思います。主体的に行動する軸を自分の中に持つ、ということを学ぶためには、学校で「1+1=2」という答えを教えることよりも、それを自分なりに考える時間が大切。答えがわからない問いに向かい合う時間が大切だということは、僕がアートに見出している可能性と重なります。個人の独創性、想像力の具現化がアートの特性ですから、すごく大きな目標としては、レジデンスにアーティストが滞在制作することを通して、多様な同時代性が存在していることをこの地域で受け入れるきっかけになったらいいな、と思ってます。
第2回は、田んぼの株かきの経験からテーマを考えた
◉まず第1弾が2015年の年末年始に公募され、2月10日から3人のアーティストが1カ月半滞在していました。そこで確認できたこと、わかったことは何かありますか?
去年は「山・雪・生活」をテーマに「奇跡を起こすアーティスト」というテーマで公募し、日本から松田壯統、大平由香里、香港からJolene MOKという3人のアーティストが参加しました。わかったことって難しいんですが、アーティストの本気を感じて、うれしかったです。松田壯統さんは、雪景色の中に呼吸を見出して重ねることで、今この瞬間に、世界が呼吸していることを感じさせてくれました。大平ゆかりさんは9メートルの屏風に北アルプス山脈を描いて、山のエネルギーを凝縮してくれました。Jolene Mokさんは大町で8つ家庭を訪れ、そこで生活する住人の名前の由来を語ることを通して、脈々と受け継がれ変化する雪国の生活風景を映像で記録してくれました。3人とも、すごくいい作品を創ってくれたと思っています。
◉そして2016年の今秋、「時・水・稲作」をテーマに、9月15日から11月23日までアナンダ・サーン(オランダ)、エリー・キョンラン・ホ(韓国)、水谷一(日本)、マリーナ・ガスパリーニ(イタリア)の4人のアーティストが滞在し、展示を行いました。まずテーマの設定について教えてください。
前回は、地域アート的な建て前を言ってもアーティストに届かないと思って、サルを追いかけて大町の山と里の境界を2年間めぐっていた僕に会ってもらおう、という気持ちで公募のお誘い文を書いたんです。第2回はどうしようかな、と考えた時に、大町で僕が心に残っていることのひとつとして、田んぼの株かきという作業を思い出しました。朝から晩まで裸足で田んぼに入って、ほぼ同じ場所で作業しているのに、太陽の移動、水温の変化、虫や動物の登場によって瞬間がダイナミックに変化して、1日がとても長く感じたんです。東京生まれの僕には衝撃的な時間感覚で、これは大町の持つ普遍的な魅力のひとつだと感じて、今回は、「時・水・稲作」という公募テーマを設定しました。
◉そこからアーティストの選定に移られるわけですね。その選定についてはいかがですか?
広報をがんばったこともあったんですが、世界41カ国から103名の応募があったんです。昔であればヨーロッパやアメリカが大半だったと思いますが、中東や南米、ロシアからも応募が来ていて、改めてグローバルな情報社会の時代だと感じました。4名を選ぶわけですが、正直書類でわかることってすごく少ないので難しいんです。だから、応募書類を信濃あさひAIRで2日間一般公開して、いろいろな人の意見を集めて、最終的に今回の作家さんたちが選ばれました。
まだ展覧会中なので、あんまりまとまってないんですが、新しい展開ができたと思っています。海外作家が3名いたこともあって、いろいろなことが当たり前には進まないんです。買い物、取材、リサーチに手間や誤解が生まれてしまう、でも、それが面白くもある。あと、僕は鷹狩山の山頂で展示している水谷一さんの「死角の眺望」という作品が好きです。うまく言えませんが、作品の前でぼーっとすると、自分を抽象的に捉えるような、SFチックな感覚になるんです。
そして地域の人にもっとアートを面白がってもらうこと
◉佐藤さんが考える、AIRの課題はなんでしょう?
あさひAIRは市や県のAIRIS(アーティスト・イン・レジデンス in 信州)というモデル事業としてスタートしました。僕がいなきゃ続かない事業じゃ困るので、持続可能な形で軌道に乗せることが僕のミッションだと思っています。そのために大切なのは2つ。ここを切り盛りする人材の育成と、ここの場所としての面白さを磨いていくこと。
教員住宅6棟をリノベーションした空間で、どうやって作家を補助するための予算を用意するのか。今はフルサポートという形で、AIRをやっているんです。アーティスト一人につき制作費、展示費、滞在費、交通費、ワークショップも含めて算出した経費を準備しています。それとは別にコーディネーターの人件費も必要。僕はこのアーティストに対するフルサポート体制がどう変化するのかがポイントだと思っています。経験を積んだところで、次の段階として「ここはサポートしたほうがいい、ここはサポートしなくていい」ということを見極めて、プロジェクトベースの企画をしていきたい。そしてアーティストのキャリアになるようなもっと自由な形式の運営方法も模索したいですね。
先日、世田谷にある遊工房アートスペースの方とお話しさせてもらいました。1989年から都市滞在型のアーティスト・イン・レジデンスをやっている民間の団体なんです。そこでは逆にそれぞれのアーティストが家賃を払うことで、僕の立場のスタッフを雇って運営している。信濃あさひAIRは今のところ公共事業なので利益を出すことはできないですが、将来的にはそれもひとつの方法だと思います。
◉北アルプス国際芸術祭と信濃大町あさひAIRの関係性、可能性について今考えていることを教えてください。
北アルプス国際芸術祭は第一線で活躍する作家が国内外から大町に来る予定です。それに対して、信濃大町あさひAIRの役割は、地域文化を自覚していくことだと思うんです。こんな作家がいる、こんな秋祭りがある、こんな魅力があるということを楽しんで認識する。今考えているのは「大町裏アートマップ」を作りたいなと思っています。アートじゃないアート、赤瀬川原平さんたちがやっている路上観察日記みたいなものの大町版です。自然物は美しいけれど、人工物を対象に。タイトルと作品写真、製作者のコメントがあって、作品のある場所を載せてある。アート好きな人が芸術祭を回るときって、作品と作品にたどり着くための間を楽しむじゃないですか。だったら間と間をつないだら面白いんじゃないかなと(笑)。そういうものを信濃大町あさひAIRでやれれば、地域の人にもっとアートを面白がってもらえるかもしれない。それは、北アルプス芸術祭があるからこそ、生きてくるんだと思います。
行政の文化事業として、2020年の東京オリンピックに合わせて地域の文化振興は注目されています。ただ、2020年以降にどのような形になるのか、想像がつきません。日本中で増えすぎた芸術祭は縮小すると思うので「芸術祭を続けること」を目的にしてしまうと乗り遅れてしまう。芸術祭をきっかけにして起こった事象がどう続くのか、そのひとつとして僕はAIRの可能性を感じているんです。
◉2017年の、北アルプス国際芸術祭に関しては、佐藤さんはどうあればいいと思っていらっしゃいますか?
昨年はこんなことが起きたらいいな、あんなことができたらいいなと妄想していましたが、今はその段階を通り過ぎて、「どうなるのかな?」という感じです。個人的にはへんなことが起きたらいいなあと思います。普通じゃないことがいろいろ起きたほうが、人間はいろんなことに対応できるようになりますから。
人が何かを想像するから現象化する。その想いが切実であればあるほど、それは独特なものになると思うんです。昨年は自分の切実さを高めようとしたんですけど、北アルプス国際芸術祭は話が大きすぎて、もっと自分の庭で切実さをやらないと混濁して伝わらないことに気がついたんです。
「想像すれば創造できる」ということが原理だとすれば、その原理に基づいて切実な想いのある人を応援したい。そして、国内外の作家と同様に、地域の切実な人たちと出会いたいです。その人たちを社会とつなげる、というと少し大げさですが、この社会構造の中でテーマを設定したり、場を設定をしたりすることから始めてみようと思います。
1981年東京都生まれ。
2006年ロンドンメトロポリタン大学建築学部空間芸術科卒、
2009年東京芸術大学大学院美術研究科鈴木理策研究室修了。
20年にパリ国立芸術学院の教授だった造形作家・川俣正氏の助手および編集の仕事に3年間携わる。
2012年より祖母が暮らす大町に引っ越し、
市役所の鳥獣被害対策員として2年間つとめた後、信濃大町あさひAIRのコーディネーターとなる。
「SOURCEPANIC」(無意識がパニック、魂を喜ばせ)というアート系ZINEも発行。