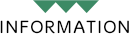[ようこそ、信州へ #003]三島有紀子さん(映画監督)

今年もにぎやかなゲスト陣とともに、手作りの映画祭、小津安二郎記念・蓼科高原映画祭が始まる。2012年の『しあわせのパン』以来、二度目の参加となる三島有紀子監督を都内でキャッチ!中谷美紀主演の《繕い裁つ人》について、映画監督としての思いについて聞いた。
「《しあわせのパン》でうかがった時は、(茅野の)新星劇場で本当にたくさんの方に観ていただいたんですよ。蓼科高原映画祭は、映画に対する愛情がとても深いので、また呼んでいただけてうれしいです。そうそう(笑)、私の税理士さん、茅野の方なんです。ひょんなことから映画祭で出会ったスタッフの方にお願いすることになって、とても助かっています」。三島監督は開口いちばんそう言うと、照れるように、恥ずかしそうに笑う。物腰の柔らかさ、穏やかな口調からは、とても大勢の屈強なスタッフを率いる!映画監督然としたといった印象はない。けれど、いや、だからだろう、こと映画に対する真摯な思いがこちらに染み渡るがごとく伝わってきたーー。インターネットには少し、いやだいぶ長いインタビューだけれど、やっぱりまとめておきたい。
「うちの父親がスーツしか着ない人で、いつも神戸のテーラーさんで仕立ててもらっていたんです。夏物、冬物、相物、タキシードと全部で8着くらいでしたが生涯大切にしていました。小さいころから私をよくテーラーさんに連れていって、生地を選ぶところから同席させ、職人さんの素晴らしさ、その手から生まれたものはただの物体ではなく、作った人の想いや考え方、生き方すべてが集約されているものだと教えてくれ、『私は服ではなく職人の誇りをまとってるんだ』なんてキザなことを言ってました。そのころからぼんやりと仕立て屋さんの映画を作れたらいいなと思っていたんです。
8年くらい前に仕立て屋さんや洋裁店を取材させていただいていて、その時に必ず『今まで作った中でいちばん印象に残っている服はなんですか』と質問してきたんです。ある大阪の洋裁師の方が『車椅子の方のために作ったウェディングドレス』とおっしゃったのを聞いて、その人のためだけに作るオーダーメイドということを深く見つめたい、と。そして改めて仕立て屋さんの映画を撮ろうと思ったんです」
三島監督は自身で脚本を書き、企画書を持って制作会社を回り、出資してくれる方を求めて動き回る日々を送る。劇映画《刺青 〜匂ひ月のごとく〜》で監督デビューはしていたが、これがほぼ初めての本格的な映画だった。
「企画を持ち込んだところで基本的には門前払いですから、会ってくれた、読んでくれたで一気一憂していました。そんな中で、原作があればできるかもしれないとアドバイスしてくれた方がいたんです。それで、いろいろ探してみたら《繕い裁つ人》という素敵な漫画に出会えた。主人公の市江さんは、私の父が語っていたような誇り高い職人で、言葉少なく、ストイックに服作りに向かっている女性。しかもお客さんのオーダーをそのまま形にするのではなく、その人が本当に求めていることは何かをじっと観察して、それを盛り込むんです。その服を着た人たちは最初はオーダーと違うと文句を言いつつも、結果的には本来なりたかった自分にたどり着ける。この市江さんを描きたい、寄り添っていきたいと。それで出版元の講談社さんに相談してオッケーをいただいたんです。ちょうど《しあわせのパン》が公開された直後ですね。この《しあわせのパン》がなかったら世の中、何も動きませんでした(苦笑)」
脚本は《永遠の0》《白ゆき姫殺人事件》を手がけている林民夫氏に白羽の矢を立てた。二人の中では「職人さんの話だから、せりふではなく作った物でお客さんの背中を押す、行動を変えていくというコミュニケーションの仕方を目指そう」「車椅子のウェディングドレスのエピソードを盛り込みたい」などの確認をする。脚本ができ上がり、主演に中谷美紀さんの出演も決まり、資金集めも本格化していく。
ところが撮影費の確保についてはいっこうに明るい光は見えてこなかった。つまりなかなかクランクインできないのだ。
「お金が集まらないので、中谷さんにスケジュールをお返ししたことが二回あったんですよ。本当にできないかもしれないという瞬間が何回あったことか。市江さんがこだわっている服をちゃちにはできない、彼女の生き方が出る服を作るにはそこそこのお金がかかる。それ以外の美術にはお金がかけられず、本当に自主映画みたいなものです。もういろんなことが八方塞がりで、こんな状態で生まれてくる映画では自分の目指すものにはならないだろう、ただ映画館で流すだけの作品になってしまうのではないかと思った日があったんです。各方面に迷惑をかけ、自分に嘘をつくんだったら作らないほうがいいと。その日の夜、スタッフルームで、もちろん監督なのでそういう暗い話はしないんですけど、自分たちが目指しているものにならないのではという空気が漂っていた。そんな中で一人が『カメラがあって役者がいれば映画になるとある監督が言ってた』と言ってくれたんです。その時に『そうや! この作品には中谷美紀という役者がいる! 地面に線を引いただけで建物がなくても洋裁店が見せられるんじゃないか、彼女が縫う仕草をすればそこにミシンが見えるんじゃないか、中谷美紀がいれば映画になる』と覚悟したんです。それでも撮るんだ、撮ったら何かが伝わるんだと信じたんですね。その日がすべての分岐点でした」
スタッフの必死のロケハンのおかげで、存在感とパワーがある撮影場所が見つかる。もちろんトントン拍子とは言えないが映画は完成し、ついに公開された。
「言葉にするのは難しいんですけど、私は、映画は公開初日に生まれると感じている。さすがに初日は感慨深いものがありました。出産したことはないけれど、難産の子がやっと生まれてきてくれたような。みんなの前では泣かなかったけど、一人になった時に…。
取材の時にはよくお父様はご覧になられたんですかとよく聞かれたんですけど、もう15年前に亡くなっていて。それに自分ではそんなに父親に見せたいという欲求もなかった。ところがお伊勢さんの新富座で初めて純粋にお客として見た時に、なぜか父親には見せられないんだという思いが湧いてきて涙があふれたんです。根底にはあったんでしょうね。亡くなっているし、そんなん思っても仕方がないとふたをしていたのかもしれない」
少し目をうるませつつ、三島監督はまた照れ笑いして、カフェオレを口に運ぶ。
「映画監督になりたい、ではないんですよね。映画を作りたい、なんです。やりたいこと、作りたいこと、こういうものが撮りたいんだという思いがあふれてくると吐きそうになる。特に助監督時代は表現したいことがあるのに吐き出せない、その衝動をどうしたらいいんだと苦しかった。だから映画監督というものになれば撮れるのか、ということなんです」
彼女の原点は、1948年のイギリス映画《赤い靴》だ。
「アンデルセンの童話がベースの映画なんです。主人公のバレリーナが作曲家と恋に落ちるんですけど、主役にも抜擢されて、バレエ団の団長から仕事か結婚かを選べみたいなことを言われて、最後、彼女はどちらも選べずに列車に飛び込んで死んでしまうという結末でした。4歳の私には、自ら命を絶つということが衝撃的すぎて1週間くらい眠れなかったんです」
4歳で自ら命を絶つことの意味を理解するというのもすごいが、この映画が実は、少女だった三島監督の心に強烈に刻みこまれ、圧倒的な影響を及ぼす。それからほんの1年あまり経ったころ、ある出来事のために本当に命を絶とうとした経験をする。
「台所にある包丁で胸を刺せば死ねるんだ、窓から飛び降りれば死ねるんだ、という中で《赤い靴》のことを思い出したんですね。あの主人公は死んでしまった。でも逆に言えば、いつでも死ねる、今日じゃなくて明日にしよう、という毎日を送っていたんです。明日、明日と思っているうちに生きることができた。自殺を描いた映画が私を生きさせてくれた。自殺とは、この世から自分の存在を消してしまいたいということですよね。それはわかった、私は自分の肉体を否定していたから。そのころは自分を自分が見ているという感覚がよくあって、この子を刺せば、この世から消えることができる、だから究極耐えられなくなったら刺してあげよう、屋上から突き落としてあげればいいんだと思いながら過ごしていたんです。だから自分の中で死イコール《赤い靴》だった。彼女は死を選んでいる、私はとりあえず生を選んでいる、毎日毎日が選択です。生きることを選んでいるという認識をさせてくれたのが《赤い靴》なんです。その状態は中学くらいまで続きましたが、やがて肉体の自分と考えている自分が一体化して、自然にそういう感覚がなくなった」
その症状はすっかり過去のものだ。その後の三島監督は、先に書いたようにどん欲に映画に立ち向かっている。まるで、それが彼女にとっての存在証明であるかのように。しかし同時に、当時の経験は、彼女にとってある種の心の支えであるかのように。映画監督として生きる彼女はむしろ、頼もしい。
「自分がここにこうして生きていられるのは映画のおかげだというのが本心だから、そのくらいの力を持っている映画を自分で作りたいし、私みたいな人間が生きていける映画を作りたいなと思うんです。もちろんそこまでの映画が作れているかというとまだまだ。だから、そういうことも含めてすべてが映画作りの糧になっていると信じたいですね。映画を作りたいという衝動もそういう経験がなかったら生まれてないのかもしれない。普通に仕事をして、結婚して穏やかに生きて行くということに満足していたかもしれない、わからないけれど」
この日、二度目に涙ぐんだ姿はさっきとは意味が違うものだ。もしかしたら聞いてはいけないことだったかもしれないが「嘘はつけへんから」と語り出してくれた言葉に救われた。彼女の撮る映画は、いつでも手に届く本棚に入れておきたい、そして何かの拍子に必ず見直したくなる作品たちだと思う。《しあわせのパン》《ぶどうのなみだ》《繕い裁つ人》も、せわしい日々の中をひととき立ち止まらせ、自分を見直させてくれる力がある。
「リアリティーを持って描きたい映画の時はとことんリアルに描きたい。でも日本ではあんまり受け入れられないファンタジックな映画も撮っていきたい。よく雰囲気って言われるんですけど、私の中ではすごく心が傷ついた時に夢の扉を開けたい、もしかしたらこういう世界があるのかもしれないと。ただ、たぶん、そこまで深いものができているかはわからないんですけど、共通しているのは死かなって思います。お客さんがそこまで受け取れるものになっていないのかもしれないけど。あ、決して自分に自殺願望があるわけでは全くないんですけど、やっぱり近いんです」
笑顔が再び戻った三島監督には、今現在「これを絶対やる!」と思っている企画が3本あるという。この5年以内にそれを実現するために忙しく動き回っている。そして、その間にもアイデアが生まれ、メモになり、企画書になっていく。いっぱいの本やDVD、中には未だにレーザーディスクもあるらしいが、ある意味、彼女にとっての生活感がもっともあふれた部屋の中でさまざまな企画が外に出るのを今か今かと待っている。
「この先に撮りたいものを入れるともっともっとあって、今も吐きそうです(笑)。オリジナルもあるし原作もある。この俳優さんでこういう人物を撮ってみたい、こういう物語をやってみたい、とか。それがなくなれば、やめればいい。いつまで撮れるかわかりませんが…。でも今あふれているものを実現させていったら、死んでも終わらないですけど(苦笑)」
カフェを出るころ、雨はあがっていた。
大阪市出身。18歳からインディーズ映画を撮り始め、神戸女学院大学卒業後、NHKに入局。
『NHKスペシャル』『トップランナー』など「人生に突然ふりかかる出来事から受ける、心の痛みと再生」をテーマに
一貫して市井を生きる人々のドキュメンタリー作品を企画・監督。
11年間の在籍を経て独立後、『刺青~匂ひ月のごとく~』で映画監督デビュー。
オリジナル脚本で監督も務めた『しあわせのパン』は、同名小説も執筆し、ともにヒットを記録した。
14年10月には『ぶどうのなみだ』を発表。第38回モントリオール世界映画祭のワールド・グレイツ部門に招待された。
映画監督としての仕事に加えて、TV向けドラマ作品や小説、エッセイの執筆等、幅広い活動で、
柔らかなアプローチの中に熱い想いを秘めた作品を手がけるクリエイターとして評価を受けている。
著作に小説「しあわせのパン」(ポプラ社)、小説「ぶどうのなみだ」(PARCO出版)がある。
ブログへ