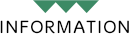[ようこそ、信州へ #020]川本嘉子(ヴィオラ奏者)

©島崎陽子
小山実稚恵さんと私のデュオのために
権代敦彦さんが書かれた曲を
松本で世界初演できる喜びとともに
人気・実力ともに日本を代表するピアニスト・小山実稚恵は『12年間・24回リサイタルシリーズ』(2006〜17)や『ベートーヴェン、そして…』(2019〜21)など、その企画性でも高く評価されている。ヴィオラの川本嘉子は1992年にジュネーヴ国際音楽コンクールヴィオラ部門で最高位を受賞し、都響やNHK交響楽団の首席客演奏者を務めるほか、世界一流のソリストや著名な指揮者らとも共演、高い評価を得ている。そして言うまでもないが「セイジ・オザワ松本 フェスティバル」の常連でもある。ピアノとヴィオラのデュオなど長年にわたって共演を重ね、互いに深い共感と信頼で結ばれた二人が、ブラームスの遺作に加え、作曲家・権代敦彦に委嘱した新曲の世界初演で松本に至福の時を届けてくれる。川本嘉子にその思いを聞いた。 公演情報はこちら
目立つことよりも、演奏の下支えとメロディの橋渡しをするのが楽しい。
――川本さんはヴァイオリンからヴィオラに楽器を転向されていらっしゃるんですよね。
川本 子どものころから「室内楽のためにヴァイオリンのレッスンに通っていた」ぐらいの思いがあって。ほかの演奏者とアンサンブルするのが大好きで、楽器をヴァイオリンからヴィオラに変えたのも、そのことが理由だったんです。ソリストとしてヴィオラを勉強されている方はたくさんいらっしゃるのに、アンサンブルを一生懸命にやっている方はあまりいなかったから。
とはいえ、私はヴィオラを個人的に教わった先生がいないんですよ。ブラームスだったら山崎伸子先生にお伺いを立てるといった感じで、その時々に応じて、お詳しい先生のレッスンを受けてきました。自分でコンクールに応募し、たまたま良い成績を収めたこともあり、とにかくアンサンブルのもとであるオーケストラや室内楽のヴィオラパートを手探りで始めて今に至ります。でも確かなのは、年に1回のOMFがなければ、ヴィオラをここまで熱心に続けていなかったと思います。私は才能教育研究会の出身で、子どものころから夏期学校で松本市に通っていて、もう松本の空気が私のDNAの一部になっているんです。夏に松本に来ることで1年頑張れるというサイクルの人生ですよ。
――ヴィオラの魅力はどんなところに感じていらっしゃいますか。
川本 表に立たないので目立たないことです(笑)。ファースト・ヴァイオリンは目立つじゃないですか。私は縁の下の力持ちじゃないけれど、下支えとメロディの橋渡しをするのがめちゃくちゃ楽しい。演奏がより良くなるためにどんなことをしたらいいかを考えるのが好きなんです。オーケストラでも差し出がましいと思いつつも、自分が考えた弾き方や工夫をやってみて、巨匠が喜んでくれたり、今までこんなやり方があるとは気が付かなかったと指揮者がおっしゃってくれたりするのがうれしいんです。また室内楽で勉強したことがオーケストラで役立ったり、オーケストラで鍛えた筋肉を室内楽で生かせるなど、自分へのフィードバックにもなっています。そういう中で、たまにソロで目立つのもなかなかの快感ですけどね(笑)。音楽家として、いろいろなことをやってみる、それが私の生き方かと思います。

提供:トリトン・アーツ・ネットワーク 撮影:大窪道治
――ステージ上のいろいろなシチュエーションに合わせて、ヴィオラの役割を楽しんでいるような感じなんでしょうか。
川本 そうですね。表で美しいメロディを弾くことや、チェロなどの低音楽器がベースラインを弾くことは誰でも容易に想像がつきますよね。でもヴィオラのパートがやらなければいけないことはどうでしょう? 私の思うヴィオラの役割は言ってみれば名前のない家事のようなものだと思っています。通常、ゴミを捨てるのは指定の袋に入れて、指定の日、指定の場所に出すというのが普通の流れですよね? 賢い主婦たちはプラスの作業としてゴミ袋をスムーズに取り出すための準備や工夫をすると思います。それ自体は、別に手を抜いても怒られないし、誰にも迷惑もかからない。だけど、やっておくことでささやかな喜びがある。名もなき家事って無限にあるじゃないですか。それを狙ってお膳立てするのがヴィオラの役割と似ている感じがします。実際の家事ではそんなことまったくやりませんけど(笑)。
――でもヴァイオリンは花形の部分があるじゃないですか。続けていたらどんなふうになっていただろうと考えたりなさらないんですか?
川本 ありますよ。才能教育では耳で聞くことで直ぐに弾けるという教育を受けていたので、あまり時間かからずにヴァイオリンは弾けたんですよ。みんなが苦労するコンチェルトくらいまでは、さほど努力しなくても弾けました。でもそれが自分にとっての違和感だったんです。友だちは、1日最低6時間は絶対練習するという人も少なくありません。私も一応6時間練習はしていたけれど、なぜやらなきゃいけないんだろうと思っていました。周りの人たちが1カ月くらいかけて仕上げる曲が1週間でできてしまう。その状況が何か居心地悪かったんです。ところがヴィオラは楽器を持つだけで疲れるし、譜面は読めないし、楽譜に書かれた音をどうしたらうまく演奏できるのかわからないし、なぜ作曲家はここまで変な音の集合体を書き並べたのか考えることで頭がいっぱいになったんです(註:ヴィオラの譜面はアルト記号(ハ音記号)を使って書かれていて、ト音記号やへ音記号のようにすいすいとは読めない)。それが私の中で充足感につながったんです。ヴィオラを始めたことで、パンドラの箱を開けちゃった感じですね。
音ではなく、空気や波動で合わせる演奏が心地いい
――小山さんと川本さんの出会いについて教えていただけますか。
川本 まだ私が若いころ、彩の国さいたま芸術劇場の館長・諸井誠さんに推薦いただいて、小山さんの企画、室内楽シリーズで何回かブラームスを弾かせていただきました。私にとって巨匠の方々とご一緒する機会を持つことができだけでうれしかったんですけど、小山さんは当時からいつか一緒にと思ってくださっていたそうで、ようやくデュオが実現したんです。
今や人生の半分ぐらいはお世話になっているのかな。もちろん頻繁に演奏しているわけではないし、10年くらい飛んだ時もありました。でもその間も小山さんの演奏はテレビや演奏会で拝聴していて、ただただ素晴らしい方だと思っています。本当に巨匠なのに、たおやかというか、肩に力が入っていらっしゃらない。私は大きなヴィオラを肩に乗せて弾いているので肩の力は抜けないということもあり、全くの真逆! だからこそ尊敬し、憧れているんです。見た目の優雅さとは違い、いざ音楽となったときのご自分への厳しさにこちらも背筋が伸びます。その一方で、小山さんも私も笑い上戸で、それこそ箸が転がっただけで爆笑! という感じなんです。笑いの沸点が低すぎて、誰かのオヤジギャグでも爆笑できる。笑いが止まらなくて、周りに迷惑をかけてしまいます。
小山さんは人の音を聞いて合わせるのではなく、空気で合わせてくださるんですよね。私も波動で合わせられたらいいなあと思っているので、そういうところも楽しい。それが合わなかったとしても、こんなにズレちゃいましたねって笑い合えるのですごく居心地がいいんです。でも本番になると小山さんは懐が深くて、うわっ! て感動しながら弾いているので、気がつくと興奮しすぎて演奏中のことを覚えていなかったりするんです。

©ND Chow
――素敵なコンビですね。でもピアノとヴィオラのデュオって、それなりにあるものなんですか?
川本 確かにあまり聞いたことはないですね。ユーリ・バシュメットさんのデビュー当時はピアノのスヴャトスラフ・リヒテルさんの秘蔵っ子みたいな感じで衝撃がありましたけど、リヒテルさんが亡くなってからは決まったピアニストはいらっしゃらないようですね。
ヴァイオリンに比べてヴィオラやチェロは曲が少ないんです。だからヴァイオリンにはデュオグループがあるし、デュオを組んでいても曲がたくさんあるので目指す先があるのだろうと思いますが、ヴィオラのレパートリーは少ししかないのですぐに一巡してしまう。だから、次にこの曲を弾くときは別のピアニストで刺激されたいと思ってしまいます。
だけど小山さんは「ブラームスは一生やっていても勉強になる」とおっしゃってくださって感謝しています。特にソナタは、ブラームスの思いも強く、濃いエッセンスが詰まっている。そういうことも含めて、小山さんの別の活動にいい影響を及ぼしていると思いますし、及んでもらわないと困る! と私はそれほど責任を感じています。私たちのデュオはピアノに比べてヴィオラの方が音が圧倒的に少ないので申し訳ないと思っています。素晴らしい方と演奏するときは自分のエゴが介入しないようにひたすら気をつけています。そして、ブラームスに対しても、謙虚にやらなければと気を引き締めてやっています。
――今回のプログラムはどのように決められたんですか。
川本 東京の第一生命ホールで小山さんのシリーズにデュオとして出演させていただいて、1回目でブラームス ソナタ1番、2回目で2番を演奏させていただきました。一昨年の暮れに行った2番の演奏会の後「今度は1番と2番を続けて弾いてみたい。第一生命ホールだけじゃなくて、いろんなところでやりたい」とおっしゃってくださいました。その二人の願いが実現した最初の演奏会が松本なんです。どうなるのか? と私自身も期待で胸が膨らんでいます。
世界初演はかなりの緊張感がある
――もう一つ、新曲『無言のコラール集』の世界初演があります。ドキドキしますね。
川本 もうドキドキですよ、本当に(笑)。これは権代さんそのものみたいな曲です。権代さんは教会でオルガンを弾いていて、バッハのような生活をお一人でしていらっしゃるイメージの方です。最近バシュメットに依頼されてコンクールのためにいろいろと曲を書いてらっしゃることでヴィオラにも造詣が深くなられた、というところで作曲をお願いしたので、思いの丈を書いてくださったようで。すごく大変(笑)。演奏もですけど、本番で要求される集中力が半端ではなく、今から不安です。
権代さんはリハーサルするときにテンポの合図をくださるのですけれど、譜面に書かれているメトロノームのテンポと寸分たがわないんですよ。むしろ権代さんの方が正確なんです(笑)。逆に私はそういうのが苦手なので、変わるテンポの数の分だけメトロノームを置いて、テンポが変わったら次を見て練習していますが、指示されたテンポ通りに弾かなければならないプレッシャーがかなりあります。1拍で10数個も音が果たして入り切るのかどうか、それを音楽的に仕上げていけるのか、本当に不安ですね。
――権代さんにはどんなふうに作曲のご依頼をされたんですか。
川本 ブラームスにバッハと同じコラール(賛美歌)をもとにした『11のコラールの前奏曲』という曲があるんです。それをさらにフェルッチョ・ブゾーニがオルガン曲からピアノ版に直していて、どれも素晴らしい曲ばかりです。そこから私が4曲をピックアップして、野平一郎さんの奥さんである多美さんにヴィオラとピアノ版に編曲していただきました。それを小山さんと何回か演奏させてもらっているうちに「こういう現代の曲があってもいいね」という話になって。バッハでもブラームスでもない、現代の曲。そうしたら小山さんから権代さんのお名前が挙がったんです。
権代さんは私にとって桐朋女子高等学校の先輩で、才気あふれる方だと存じ上げていましたし、プロになってからもいろいろな音楽祭やプロジェクトで曲を弾いていて素晴らしいと感じていました。そして歴史上の作曲家がたどっている大道に沿って音楽をつくっていらっしゃる。もちろん権代さんの作品が私たちのためにできることは大賛成で、小山さんが委嘱してくださいました。あれほど素晴らしいピアニストが大作曲家に委嘱してくれた事実がヴィオラ界にとっての快挙です。
――『無言のコラール集』が松本で、正真正銘の初演として弾かれるんですよね。
川本 5曲のうち3曲は3月に小山さんの越谷のサンシティホールのコンサートで急きょプログラムに入れていただきました。残りの2曲は今回が初御披露目なので全曲の世界初演は松本ということになります。
権代作品は緩急の激しい曲で、急の部分が経験がないほど圧迫感を伴います。小山さんとのリハーサルはマスクが必須なのに、かなり激しく弾き続けるので、私が毎回呼吸困難になってしまうのです。呼吸が整うまで少し時間がかかってしまうくらいですが、なぜかそこで面白スイッチが入ってしまい、二人でまた爆笑してもっと苦しくなるということもたびたびです。

©島崎陽子
――世界初演をするというお気持ちはどんな感じなのですか?
川本 オーケストラでも室内楽でもたまに体験しますが、世界初演は名前も残るので緊張感はかなりあります。一番緊張するのは作曲してくださった権代さんご本人の前で弾くことです。楽譜通りにできなかったりすると申し訳ないですから。それに私ができなくても10年後くらいに若い演奏家が簡単にクリアして権代さんが「川本にはがっかりだな」と思われるのも怖い。そういうことまで考えて、何ごともないように仕上げようと思っています。