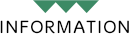[聞く/entre+voir #030]串田和美(「FESTA松本」総合ディレクター)

撮影:山田毅
人の心を動かすような大きな熱量、
うねりを起こせるようなフェスティバルを
市民の皆さんと一緒に目指したい
「FESTA松本」が2021年10月に初開催される。まつもと市民芸術館の串田和美総監督が、2023年3月の任期終了を控え、総合ディレクターとして大きな花火を打ち上げる。まつもと市民芸術館の主催公演、TCアルプのメンバーが作・演出を手がける公演、これまで芸術館に参加してきたゆかりの俳優・ミュージシャンによる公演、はたまた初参加の公演など多彩で自由なラインナップが並ぶ。自らも演出、出演にと八面六臂の串田さんに話を伺った。

困難だからこそ祭りをやるべき
――待望の松本での演劇祭ですね。
串田 待望でもあるけど、大変でもあるよ(笑)。
――串田さんの中では、芸術監督就任の話があったときから柱の一つとして掲げていたものでした。
串田 そうだね。自主制作、学校、広報誌、文芸部、そしてフェスティバルが芸術館が始まるときに抱いていた5本柱。当時の市長さんからはサイトウ・キネン・フェスティバル松本と両輪で文化を、街を盛り上げてほしいと言われて「それは大変だ」と思ったけれど、もう一方の車輪として何ができるかはずっと考えていた。それが建設反対派の市長さんが当選し、とてもじゃないけれどフェスティバルなんて口に出せる状態ではなくなった。そしてさらに新しい市長さんになり、僕も芸術監督としての任期に区切りをつけることになって、だったらやれることをと、思い切ってフェスティバルを実施することにしたわけです。
――「FESTA松本」はどういうイメージを持っていらっしゃるんですか?
串田 いろいろイメージはあるけど、それを貫こうとするのが大変。フェスティバルをやるには、たくさんのスポンサーがいるとか、国や行政の助成金を取らないとできないと思われているけど、そうじゃない方法があるだろうとずっと思っていたんです。特に助成金は、1960年代から演劇を始めた人間としては憧れであり夢でもあったけれど、僕が生きているうちには実現しないだろうと思っていた。けれど20世紀後半から叶い始めたでしょ。それは素晴らしいことでもあるんですけど、同時に演劇のあり方、観客との関係など崩れてきていることもある。いや、そこに意固地にしがみつくことこそ滑稽かもしれない。でも僕にとって譲れない大切なこともある。
――「フェスティバル=“お祭り”というものは決して社会が安泰で裕福な時にだけ行われるものではありません。むしろ我々人間が困難な災難に見舞われた時にこそ」必要だという挨拶文が印象的でした。
串田 コロナのことをどう捉えるか、ですよね。コロナってなんだ?ということです。それは感染症としてのコロナではなく、いろんなことを考え直すいい機会だと思います。人間が科学や医療ですべてを封じ込めていくことがいいのかどうか、もちろんそれに頼るしかないんだけども。コロナも地震、台風、津波なんかと同じ自然の猛威であって、また動物や植物などほかの生命体との戦い。じゃあどうやって共存していくのか。僕らはそういう地球で生きているわけです。コロナがあるから自粛すると言っていたら、ずっと自粛し続けないといけない。そして困難は何度も起きているわけで、そのたびに人類は科学的な進歩、経済的な発展という言葉でごまかしてきてはいないか。もし祭りの役割が平和な社会生活が戻るように祈りを込めたり、心を健全に保ったり、人類がこれから先の生き方を見つけるために行われるものだとしたら、困難だからこそやるべきだと僕は思っています。もちろんこの社会に生きているから、そういう状況も背負って僕らは演劇をつくっている。僕の場合は直接的には表現しないけれど、そういう思いが常に根底にはあるんです。
ユートピアのような時間が生まれるのがフェスティバル

撮影:山田毅
――串田さんは、これまで参加してきたフランスのアヴィニョン、ルーマニアのシビウなどのフェスティバルのお話もよくされますが、それらのイメージもおありになるんですか?
串田 あると言えば、ある。でもそれは目的ではないかな。1994年に最初にアヴィニョンに呼ばれて、渡邊守章さん、太田省吾さん、佐藤信さんたちと討論会をしたんだよね。そのときは公演はなかったんだけど、こんな素敵なフェスティバルがあるんだと感動して、次の年に『スカパン』を持っていきました。フェスティバルに対する感動というのは表面的な部分もあるんだけど、ユートピアのような時間が流れる瞬間、瞬間を体験できたこと。メインには太陽劇団のアリアーヌ・ムニューシキン、世界的な演出家のピーター・ブルックのビッグネームがいる。一方では広場でチャンスをつかもうと死に物狂いの人たちもいるし、小さな車に荷物を詰め込んで大陸を横断しているような小さなサーカス団もいる。そんな中で郊外を散歩していたら、大きなお屋敷の大きな庭で、京劇役者が踊っているのを学ぶようにピナ・バウシュが真剣に見つめていたのを垣根越しに見たんだよね。何本も作品を見たけれど、その風景こそが衝撃的で、感動した。海外のフェスティバルがお手本になる部分もあるけれど、日本では難しいなって思うこともある。でもどこにもないものができたらいいなというのが本当の気持ちですね。
――「FESTA松本」で実現したいと思ったことはなんですか?
串田 一番は、作品をつくること、フェスティバルを成り立たせることに、市民の皆さんとどう関われるのかな、ということですね。無関係にこっちでやって、「わあ、にぎわっているね」「すごい人たちを呼んでくれてありがとう」という関係では意味がない。受付をお願いする、ポスターを貼ってもらう、友達に紹介してもらう、いろいろな応援の仕方があるけれど、市民の皆さんと一緒につくっている、つながっていると思えることが目標の一つですね。作品一つ一つは素材であって、大きな熱量、うねりみたいなものが人の心を動かすものになる、それを一緒に起こしたい、そういうことかな。
――ラインナップの数も内容も初回から攻めてます! 串田さんはじめ、TCアルプの皆さんも大活躍ですね。
串田 これだけの数の公演を呼んだら大変だからねえ(笑)。今、アルプと、新アルプ、演劇工場を卒業したメンバーを含めると16人になります。アルプのメンバーは2、3作品に参加する。長く所属しているメンバーほどガンガン動いていますよ。
――「太陽企画」「惑星企画」「衛星企画」と宇宙になぞらえたグループ分けにはどんな理由があるんですか?
串田 普通に言えば、メインである招待公演、オフ、自由参加のフリンジということになるんだろうけど、そうすると上下関係を表しているみたいになる。招待作品と言えばそれだけで価値があると思ってしまいがちだけど、どんなに小さなものにも価値はあるし、基準は僕らが押しつけるものではなく、お客さんが自分にとって最高だと感じてくださればいいもの。日本人は特にそうだけれど、物を買うときでもブランドを重視して自分にとっての価値を大事にしないところがあるじゃない。私の価値観、私の一番でいいじゃない。でもいろんな制約もあるから区分けは必要で、宇宙に関する言葉にしました。そこにどういう意味があるかは、お客さんが考えてくださればいいと思います。

――ラインナップはこれで確定ということですか?
串田 そうだね。片方では「固めなきゃいけない」という気持ちもあるんだけど、もう片方では「固めたくない」というのもあるんですよ。フェスティバルをやると行ったら「水くさいなあ、俺も行くよ」といろいろな人が声をかけてくれる。でもこういうことってよくあるじゃない。「予算ないんだよ」と伝えると、少し間が空いて「そんなの気にするなよ」みたいなことがさ。でも、せっかく来てくれるのに、勝手に来て勝手にやってというわけにもいかない(笑)。またフラッとやってきて歌ったり演じてくれる人がいたらうれしいしね。紙のプログラムには載らなくても、意外なことが起こるかもしれない、なるべくそういうスタンスでいたいですね。本当は僕らも含めてこの期間の松本市に作品を持ち寄ってくるというふうになればいいんだけど、それはとても贅沢なこと。一方で予算があるから、その時期にたくさん呼んだという形にだけはしたくないですね。だから役者もミュージシャンも「こういうところでできたな、やればよかったな、次回はやってみよう」という感じで成長していかれればいいなあと思っています。
――それは確かに日本のフェスティバルにはない形かもしれませんね。
串田 2021年2月に『真冬のバーレスク』という作品にも出てくれたドラムの木村おおじさんが、ピアノの小林創さんと「はじめとおおじ」というユニットを組んでいる。彼らはパン屋のスヰートさんの店で『ジョンとジョー』の合間の曲を演奏してくれるんだけど、彼らは彼らで『晩秋のツープラトン』というライブをやるし、『ワタシの青空 西遊記異聞』にも出てくれるんです。そういう横断的な交流が自然発生的に起こるといいなあ。「にぎやか茶話会」「大人のチャオ!」という企画では、ジャンルがバラバラの人たちが集まって、もちろん仕掛けはつくるんですけど偶発的に音楽が始まったり、そう思ったら話し合いになったり、即興性のある、戯曲のない演劇みたいなことをやってみようかなと思っています。
――串田さんならではの発想ですね。
串田 そう? まぁまずは皆さんに実際に何でもできるんだということを見ていただいて、理解してもらうことが大事だと思っていますね、今回は。コロナの第一波が過ぎて、あがたの森の四阿(あずまや)で一人芝居をやったじゃない? そこから続いているんですよね。あそこでやったときに「ここでもいいや」と思ったのが大きかった。お客さんが投げ銭までしてくれるんだという驚きもあったけれど、それよりすごくしっかり見てくれているということに感動したんだ。この感じ、この感じのまま10人が出るお芝居に、500人の客席に、そして松本の街中にと広げてみたい。演劇ってそこに居合わせることが大切な要素じゃない。それをもっと広げていきたいです。
それとね、戦前の浅草には文化人や芸人が集まっては歌ったり踊ったりするような飲み屋で、テーブルの真ん中に五寸釘が反対向きに打ってあるところがあったんだって。もしお代が払えない人はそこに勘定書を刺しておくと、閉店になるころには勘定書はなくなっている。誰かが必ず払うんだね。そんな夢みたいな話があるわけはないと思うんだけれど、その話を松本でしたら「お釣りは次のお客さんに使ってください」なんていう喫茶店やお菓子屋さんがあったって聞いたんです。お店の人も独り占めしたくないから、学生なんかが来たときに「半額でいいですよ」と言ったとか。そういう精神で、子どもも大人も、誰もが参加できるフェスティバルをつくりたいなあって思うんです。

撮影:山田毅