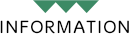[ようこそ、信州へ #013]手塚 眞(ヴィジュアリスト)

手塚家のルーツにまつわる、木曾義仲を中心にした映画を長野県で撮影したい
そのための検証を一つずつ行なっていきます
手塚治虫の長男で、ヴィジュアリストの手塚眞。20年前に坂口安吾の短編小説を題材にした『白痴』、手塚治虫の異色漫画が原作の最新作『ばるぼら』という2本の映画を引っさげて長野県に登場する。『白痴』と『ばるぼら』が長野松竹相生座・長野ロキシーと上田映劇で上映される。
分断が進む現代にこそ、20年前に撮った映画の意味が強くなってきた
『白痴』は、ヴェネチア国際映画祭をはじめ世界の映画祭で評価され、ヨーロッパで劇場公開された手塚の代表作。戦時中の秘められた男女の共同生活と逃避行を描いた原作を、イマジネーションにあふれた手塚独自の発想、クライマックスシーンで巨大なオープンセットを爆破・炎上させる大胆な演出で映像化し大きな話題を呼んだ。今回は公開20周年を記念してデジタルリマスター版として上映する。
――デジタルリマスター版として上映する経緯から教えていただけますか?
手塚 いつかはデジタル化しないと劇場公開できないので、そのきっかけを考えていたときに、公開から20年がやってきましたので、その記念として準備を始めました。とはいえそれなりの金額が必要だったものですからクラウドファンディングを実施したところ、想像以上に支援いただけたことでデジタル化が実現できました。言い換えれば劇場で見たいと思ってくださる方がそれだけいらっしゃるんだという手応えにもつながりました。
デジタルリマスター版とは言え、フィルムの良さを殺さないようにしなければいけない。重要なのは色と光を一番いい状態にすることなので、当時の撮影カメラマンさんにも来ていただいて、1カットずつ検証し直していきました。

『白痴』より
――『白痴』を撮ろう、坂口安吾を映画化しようとした思いを教えてください。
手塚 自分自身で何をつくったらいいかがわからなくなってしまった、作家として道に迷っている時期でした。心からつくりたいと思えなければつくりたくない、というくらいの意固地になっていたんです。何か突破口になるものがないか考えていたときに坂口さんの原作に出会い、これこそ探し求めていた作品だと思ったんです。読み進める間にどんどん絵が浮かんで、本を閉じたときには一本の映画を撮り終えたくらいの気持ちになりました。どうしてもこれを撮りたいと、その場で企画を考えたのですが、同時に非常に難しい企画であることも感じていました。どちらかというと思索的な内容で、内面をさまようような物語ですから、わかりやすいエンタメにはならない。にもかかわらず、これは空襲のすごさを伝えられなかったらつくる意味もないと思ったんです。その時点で実際のセットを燃やすしかないと考えていました。しかし派手なエンターテインメントでもないものに何億円もかける映画会社はないだろうと思っていたし、相談に乗ってくれるプロデューサーさえいなかった。
――それでも屈しなかった理由はなんだったんでしょう?
手塚 こんなものが本当にできるのかという自分自身へのチャレンジもありましたが、日本の映画業界で真に文化的な作品ができるかどうかを確かめようと。もしできないのなら日本映画を見限るくらいに思っていました。かといって一生これを引きずるつもりはないから、10年経って完成していなかったらキレイさっぱりあきらめようというつもりでスタートしたんです。その10年はほかから企画がきてもすべて断ってこれに集中しようと思っていました。もちろん紆余曲折はありましたが、なんとか完成し、最初に試写会をやったのが本当に10年目だったんです。一念というのは恐ろしいものだと思いました(苦笑)。
――作品に時代が追いつくという言い方があります。世界的に分断が起こり、すごく不穏な世の中になった今、『白痴』に対する思いもまた新たになっているように思います。
手塚 それは神秘的なもので理屈で考えて始めたわけではないんですよね。たまたま20年が経って、また見せなければという気持ちになった。理由はわかりません。ところが出してみたら世の中そうなっていた。おっしゃるように20年前には映画の技術や表現への評価しか出てこなかったんです。こちらの思っていることが伝わっていないのかと、すごく口惜しかった。改めて観ても内容的に響くんです。実際に映画館で公開していく中で「今の時代の映画に見えます」という声も聞きます。90年代以降、日本は格差社会になっていますし、さまざまな不安が増してきています。当時は人間の心の葛藤や矛盾を戦争を使って描いてみようと思ったわけです。それがこの映画をつくった後に、ニューヨークでの同時多発テロが起きたりすると、また戦争が起きるのかと不安が沸き起こったり、自然災害で街が壊滅するという事実が起きていくことで、みんなどこかで覚悟を決めなければとなってくる。決してありがたいことではないんですけど、それによってこの映画の意味が強くなってきていると感じています。

『白痴』より

『白痴』より
――『白痴』の売り上げは劇場の支援にもなるそうですね。
手塚 2016年に『星くず兄弟の新たな伝説』を全国のミニシアターにかけたんですけど、上映の最中にいくつかの劇場が倒産したんです。それを目の当たりにして非常にショックを受けました。インディーズ映画、独立プロの映画などが見られる場所が減ってきているという危機感もあり、守らなければという気持ちを抱いたんです。映画は文化ですから、間口は広くなくてはいけませんし、いろいろな映画を見てもらうことが文化的活動になる。そこにミニシアターの価値がすごくある。わずかであっても、そこに目を向けていただける機会をつくりたいと思いましたので、『白痴』のデジタルマスター版はミニシアター限定公開にしようと考えたわけです。
――相生座も上田映劇もとても伝統ある劇場ですが、訪ねてみていかがでしたか?
手塚 古い劇場が今も残っていて、生きているということがうれしいですよね。またそうでなければいけないという思いもあります。いずれにしても東京ではお目にかかれないような劇場ですから、うらやましいです。映画は映画館で見るものです。ここで上演してほしいなと思いましたし、実際に上演していただけることになったのはうれしいですね。

文学的主題に加え、現実か幻想かわからない不思議さもあって、つかみどころがない
その魅力をそのまま映画にしてみたかった
第32回東京国際映画祭2019・コンペティション部門の正式招待をはじめ世界各国の映画祭で大きな反響を呼んだ『ばるぼら』。原作はデカダニズムと狂気にはさまれた男の物語だ。<ばるぼら>という名前のフーテンの少女と出会った作家・美倉洋介が、小説家としての悩みを抱えながら、成功し、名声を得、それを失い、破滅していく。そこに退廃的な芸術論が盛り込まれ、随所に文学好きや芸術好きの心をくすぐる仕掛けが施されている。
――手塚治虫さんの原作の中から「ばるぼら」を選んだ理由を教えてください。
手塚 昔から好きな作品でしたので、いつか映画化できればくらいに思っていたんです。5年くらいに前に知り合いのプロデューサーとお会いしたときに、原作のことを話したら「ぜひやりましょう」となったんですよ。その質問はよくされるんですけど、本当にたまたまなんです。
子どものころから好きな作品ではありましたが、手塚漫画の中では変わったテイストではあるんです。この話はとある小説家が一人の女性に振り回されてだんだん落ちていくデカダンス。ファンタジーや不思議な話はあるけど、デカダンスを感じた作品はないんですよね。唯一かもしれない。しかも文学的主題に加え、現実か幻想かわからない不思議さもあって、つかみどころがないんです。その魅力が<ばるぼら>という女性に集約されている。最初はフーテンとして現れるのに、ミューズや魔女だと言われたり、姿が現れたり消えたり、手塚治虫自身が何も決めずに書いたのではというくらいです。それをそのまま映画にすれば哀愁にあふれた作品になるんじゃないかと思ったんです。

(C)2019『ばるぼら』製作委員会
――撮影監督にはウォン・カーウァイ監督で活躍されていたクリストファー・ドイルさんを起用したというのもポイントですね。
手塚 人間的にも面白い方なんですけど、映画に対する思いが非常に純粋な方でした。僕は映像の美学に出会いたくて映画を見てきたんですけど、日本の現在の映画は美学が足りないと思っているんです。ドイルさんを選んだ理由はそこです。最近の映画は汚い裏町が出てくると、その汚なさのまま映る。そうじゃない、美学的に汚い裏町を誰が撮れるんだろうと思ったときに、彼のことが思い出されて。今回はセクシーな映画にしようと思ったんです。男と女がセクシーなのはもちろん、街もセクシーにしたかった。汚い裏町をセクシーにしたかった。僕はお会いしたことがなかったので、駄目でもともとと英訳した台本を送ったらすぐに連絡が来たんですね。それから4年が経ってしまったんですけど、毎年「あれはいつやるんだ」「予定は調整する」と連絡をくれるほど、思い入れを持ってくださったんです。
――ドイルさんを起用したことで達成できたことはどんな部分ですか?
井田 見事にこちらが期待する絵を撮ってくれました。意外だったのはプロのカメラマンだったんですよ。つまり一番大事なのは監督の意見だと。自分のアイデアはあるけれども、まずは監督の意見を聞きたい、何回でも何時間でもミーティングしたいと最初から言ってました。こちらの狙いで、わざと1日渡す、<ばるぼら>役の二階堂ふみさんも預けるから、あなたの好きなもの、あなたが考える<ばるぼら>を撮ってほしいとお願いしました。その素材を僕が編集して、組み立てようと考えたんです。その日があいにく雨だったんですが、それがすごく素敵な絵だったので、だいぶ使わせていただきました。
――稲垣吾郎さんはいかがでしたか? きっと前の事務所だったらありえない役のようにも思います。
手塚 僕は稲垣さんのことは俳優として見ていました。彼が出ている映画も何本か見ていて、大人しいんだけど存在感がある、センシティブな演技ができる方だと感じていました。もう一つは、稲垣さんが『白痴』が好きだという話を人づてに聞いていたんです。20年前、当時SMAP、彼が20代だったころに映画館に一人で見にいらしていたと聞いていました。なかなかいいセンスしているなと(笑)。そんなこともあって、いつかご一緒したいと思っていたんですけど、非常にいい出会いでしたね。原作のニュアンスとは違うんですけど、むしろ僕の望んでいた主人公の雰囲気を出してくれたと思っています。

(C)2019『ばるぼら』製作委員会
――――話題は変わりますが、手塚家の先祖、平安時代の武将・手塚太郎光盛は長野県にルーツがありますよね。
手塚 そうなんです。この数年はそのことを強く意識してきました。これは僕の夢でもあるんですが、自分のルーツを映画にしたいんです。そこには木曾義仲が絡んできます。はっきり言えば木曾義仲を中心にした映画を撮りたいと思っています。そして、もちろん長野県下で撮影したい。これも口にするのは簡単ですが、お金がかかるでしょう。黒澤明監督並みにと想像しています(笑)。騎馬武者をどのくらい再現できるかとかこだわり出せばきりがない。当時のことですから本当は木曽駒みたいな馬がいいと思うんですけど、そういうことを一つずつ検証していきたいと思っています。時間はかかるかもしれませんが、バイタリティがあるうちに、そうですね5年くらいの間にぜひチャレンジしたいと思います。動き出すなら今かなと思っています。長野県内の自治体はもちろん、地元の皆さんのご協力をお願いしたいと思っております。