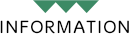[聞く/entre+voir #028]井田 亜彩実(ダンサー、振付家)

部屋の中から外部との関係を取り戻すためにはどんな表現ができるか
イマジネーションを止めなかったことから実現した初の長野公演です
長野市に井田亜彩実さんが引っ越してきたと聞いたのは、1年ほど前だったろうか。なんだかコンテンポラリーのダンサーさんがちょいちょい長野県内に移り住み始めた流れの中だった。バットシェバ、インバルピントなど名だたるカンパニーを排出するなど、イスラエルはコンテンポラリーダンスが熱いと言われて久しいが、井田さんはMARIA KONG dancers companyでプロとして活躍していた。日本ではあちこちに引っ張りだこの井田さんだが、県内ではどんな活動ができるか模索を続けていた。ダンス教室を始めたりする中で、コロナがやってきた。公演やワークショップが中止になったが、一筋の光明から、いよいよ待望の長野市芸術館リサイタルホールで12月12日にダンスとピアノの共演を果たす。
――いよいよ、長野県での初の自主公演が実現しますね。
井田 コロナが流行りはじめて、3月から公演やワークショップなど中止になって、自粛が発表された4月にはこれは長引くかもしれないと感じるようになったんです。でもダンサーって表現することをやめられないんですよね。いつもは劇場とかリハーサル室とか大きな空間で踊っているから、6畳、8畳くらいの壁に囲まれた部屋の中で動くというのがなんとも違和感があったんです。でも、めっちゃ踊りました。この状況を嘆くことは簡単だけれど、時間は止まってくれないじゃないですか。コロナが明けた時にいいスタートダッシュが切れる状態でいるには、やっぱり蓄えておくことが絶対に必要なわけです。お金もですけど、表現者として。
――それで自宅の部屋で踊りはじめたんですね。オンラインでワークショップも発信してましたよね。
井田 4〜8月上旬まで誰かと一緒に創作するということができなかったから、ひたすら自分と向き合う、自分が何をしたいか考えていました。私は本質的に人とつながるというのはどういうことかを考えていたんですよ。昨年、エーリッヒ・フロムさんの著書『愛するということ』を読んだんです。私は人間は本能的なカンや野生性を持っていると思ったんですけど、彼曰く、そういうものはもはや私たちのDNAには組み込まれておらず、代わりに自然と切り離されたことで孤独を背負っている、テクノロジーや社会背景などによって孤独を感じるシチュエーションが増えていると。まさにコロナに分断された状況に重なると思ったんですよ。そういう意味で個人個人の存在とは何かを問いかける時間になった。フロムさんは孤独から解放されるには、能動的に環境を築き上げることだと書いていましたが、私も能動的にアクションを取ることがテーマとしてあって。コロナ禍でも私の感覚は止められないわけで、相手は存在しないけれど、部屋の中から関係を取り戻すためにはどういう表現ができるのかを考えました。部屋の中ですから大きな動きはできない。それまでは感情のまま動いていたけれども、自分の感覚をシンプルに外につなげるというコンセプトで動きをつくったんです。それは余計な情報がない、私の内面から出てくる動きなわけです。場所が広いと、こんな動きができるじゃんとプラスする思考が働くわけですが、狭い空間だからとてもシンプルになる。つかむ、引っ張る、つながる、受け止める……そういう振付が少しずつ溜まってきたんですよ。
――そういう姿勢が幸運を呼び込むんですよね(笑)。
井田 そうなんです。長野県の頑張るアーティスト応援事業の募集があって、それもすごくうれしかったんですけど、コロナ禍で紡ぎあげた動きを形にしたいと思ったんです。でもYouTubeで公開となると、音楽の権利が引っかかる可能性があるじゃないですか。手伝ってくれていた映像作家の和田はる菜ちゃんと相談していたんですよ。ところがその日、私の誕生日でfacebookでつながっていた作曲家の笠松泰洋さんからメッセージが届いていたんです。実は笠松さんとはお会いしたことも、やり取りをしたこともなかった。私の師匠でもある平山素子さんの作品で曲もつくられている、いわば雲の上の存在の方ですから。その笠松さんが「おめでとう。今度一緒に何かやりたいね」と。

撮影:大洞博靖

撮影:大洞博靖
――その笠松さんの雰囲気はわかります。蜷川幸雄さんの作品の曲をつくったりしているけれど、若い才能ともクリエイションされているんですよね。ちょうど笠松さんにそんな取材をしたタイミングでした(笑)。
井田 笠松さんがお膳立てしてくださった公演はがまた素晴らしくて。舞台に立つ私たちだけではなく、ホールのスタッフの方々、お客様も含めた皆さんから芸術活動を紡いでいきたいという想いが伝わってきたんですよ。アートの可能性を信じてくださっている方々が集まってくださったんでしょうね。そういう想いの方々と共有した時間に感動しました。私はどんなふうに踊ったか覚えてないんですけど、熱量はすごく感じたんです。終演後に笠松さんが、「これだけみんなが幸せな気持ちになったのは初めて」とおっしゃってくださったのもすごくうれしかった。
笠松さんや共に演奏してくださったピアニストの松木詩奈さんの関係で、お客様は音楽ファンの方が多かったんです。普通そういう環境だと「ダンスはいらないんじゃないの」と言われがちなんですって。音楽に精通している方々からすれば、音楽を理解していないダンスはただのノイズなんでしょうね。でも、笠松さんのところには「初めて音楽とダンスが共存する素晴らさを体験した」という感想が届いたらしいんですよ。私自身、表現者としてステップを踏めた気持ちになりました。そうしたら、笠松さんが長野公演をやりましょうって背中を押してくださったんですよ。
――おめでとうございます。
井田 そうなんですよね。絶妙なタイミングだけど、社交辞令かもしれないし、お願いしてもいいものか悩んだんですけど、言うだけはタダだと思って連絡させていただきました。そうしたら「もちろん」とお返事くださって、イメージとコンセプトをお伝えしたら、翌朝には曲ができ上がってきたんです。それが素晴らしくて。そこにもう少しこうしたいんですとご相談しても気持ちよく修正してくださり、笠松さんも「いい音楽ができた」とおっしゃってくださいました。そしてさらにいい曲ができたんだから、「私にもしっかり生で踊ってほしいと」と、笠松さんご自身初めての主催公演を即決してくださったんです。お会いしたこともない私を選んでくださるとは、なんともチャレンジャーな方だと思いました。
――この作品はどんなプログラムになるのでしょうか?
井田 笠松さんは頑張れアーティスト応援事業のときにつくってくださった「グラタナス」という曲と即興を弾いてくださいます。笠松さんが作曲したほかの2曲、シューマンとバッハの曲を松木さんが弾いてくださいます。松木さんは笠松さんの愛弟子で、とっても真面目にピアノに向き合っていらっしゃる20代のピアニストです。
「グラタナス」やばいです。凄まじくいい曲をいただきました。この曲は私が今感じている想いが全部詰め込まれているんです。今までは何かに自分を投影してきたんですけど、今回は私自身です。私を表現した作品です。私の人生の財産ですし、ずっと踊っていきたいと思っています。

撮影:大洞博靖
転機は若いお坊さんに背中を押してもらったこと
――長野に来る前に暮らしていたイスラエルの話を聞かせてください。なぜイスラエルに?
井田 イスラエルが一番コンテンポラリーダンスに熱い国だからです。いろんな国の人が集まっているからか、表現の幅が広いんですね。すべてのカンパニーにすごく個性があって、なおかつ身体の強さがある。正直に言うと、かつての私は海外に行く気はまったくなかったんですよ。ビビりだったので。でも文化庁の在外研修が通り、一も二もなくMARIA KONG dancers companyを選びました。MARIA KONGは来日公演の予定もありましたが東日本大震災で中止になったんです。私はチケットを持っていて。ちょうど振付家として活動を始めたころだったので、クリエイションに力を入れているMARIA KONGの現場に立ち会えるのがすごく魅力的でした。まだ英語もしゃべれなかったんですよね。でも何も怖いものはなく、楽しみしかなかったんです。
――井田さんは富山生まれ、新潟の高校でダンス部に入り、筑波大学・大学院時代に、日本のbaby-Qに所属したり、大学では「いだくろ」というユニットで活動したりしているんですよね。
井田 振り付けを始めたのは大学院のころでした。当時は出すコンペ出すコンペで入賞していたし、在外研修も通った。運が良すぎると思いつつ、波が来ているから乗るしかないとイスラエルに行ったわけです。イスラエルに行ってからはすごい苦労しましたけど(笑)。

イスラエル時代の写真
――そのイスラエルでもっとも学んだことは?
井田 一体感を感じること、ですね。私はそれまで技術を高めること、うまく見せること、そういう外側への意識が強かったんです。とにかく繰り返し練習して振付を間違えないようにしていました。ところがイスラエルでは、もうバッサリやられましたね、あなたみたいな自己中ダンサーはいらないって。みんなで一緒に踊っているのに、あなたはどこにいるの?って。一緒に踊るということは、その時空間を共有して表現していくかということ。相手の反応によって自分の動きが変わるかもしれないし、自分の反応によって相手の動きが変わるかもしれない。あなたがうまく見えるかどうかなんてどうでもいいんだよって。周りがいて自分が存在する、あなたがいて周りが存在するんだよって言われて、目が覚めたんですよね。そうやって考えを改めた時に、目の前が開けて見えたんです。仲間の素晴らしさが見えてきて、私の表現の奥行きも広がって、この空間において私は、あなたはどうあるべきなのかを問い続けるのが表現だと気づいたんです。そして同時に、わからないことを受け入れることも大事にしようと考えるようになりました。人間は予測ができないことに直面すると不安になるし、自分でコントロールしたくなるもの。そうじゃなくて知らないことに出会えるのは、ハッピーじゃないですかというふうに考えるようになりました。
――ダンスだけでなく、人間としても変わったんですね。
井田 そう、どっちもです。人として変わればダンスの表現も変わる。ダンスは自分の鏡なんです。ダンサーは言葉で自己紹介するより、踊った方がその人のことがわかる。一人よがりだとか、テクニック重視なんだということも見えてしまう。だからダンスは怖い。でもそれはいいんです。その技術が突き抜ければ高い評価も得られる。ただ私はそういうタイプではないというだけで。
それにオープンマインドになったからこそ笠松さんに出会えたと思うんです。笠松さんは感覚が合うと言ってくださるんですけど、私もすごくやりやすい。お互いに感受性、感じるセンサーがいっぱいあって、お互いに発信することをキャッチできる感覚があります。即興では私も笠松さんの音によって動きが生まれるし、笠松さんも私の動きをよく見てくれてメロディを生み出してくれる。それは台本のない会話みたいなもので、とっても楽しいんですよ。私は自覚はないんですけど、音を理解しているって言ってくださって。「グラタナス」にしても、音にはハマっていないけど、音と動きが確立されているとおっしゃってくださる。

撮影:大洞博靖

撮影:大洞博靖
――「合ってないのに合っている」とは笠松さんも難しいことおっしゃる。
井田 たしかに自分の中で合いすぎたな、今は不協和音だったなというのはわかるんですよ。それを言語化はできません。でも音をキャッチするのは好き。そういう意味では音楽のスペシャリストの方とそういう作業をする機会を得られたのはすごくありがたいことですね。松木さんのピアノもすごく勢いがあるから、自分の力では生み出せない迫力を表現してくれる。生演奏はいいですね。アートが持つ可能性、イマジネーションや思考を止めないという行為を続けたからこその出会いだと思います。お客様とも、今回はその創造性みたいなものを共有できるのを楽しみにしています。