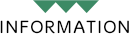【今だから芸術を語ろう】山崎 一男(「長野舞台」代表)

われわれの仕事は受け身かもしれないけれど
作品ができている陰では、多くのスタッフの時間と英知が結集されている
そのことをもっともっとアピールしていかなければと痛感した
演劇やコンサートといったホールでの催し、イベントなどのクオリティを支えてくれている存在が、舞台監督、照明、音響などの役割を担ってくれる技術関係のスタッフさん。「舞台さん」と呼ばれる彼らは、作品の芸術性を高める役割ばかりではなく、円滑にスケジュールを進めたり、安全管理にも務めてくれる頼もしい存在でもある。ただ、このコロナの影響でまったく稼働ができていない。株式会社長野舞台の代表、山崎一男さんにお話を伺った。
日本中の技術スタッフが仕事がまったくない状態
――ようやく社会が動き始めました。とは言え、ホールなどが本格的に動き始めるのはもう少し先になりそうです。現在の状況について教えてください。
山崎 2月の末、25、26日あたりに非常事態宣言が出るかもしれないという報道が流れたとき、そのころから「催しを中止します」という電話が鳴り出して、3月から催しはほとんどなくなっていきました。だから3月からほとんど仕事がない状態です。4、5月も動いているのはテレビ局の仕事、中継のときくらいでした。
――山崎さんは長野県舞台技術者協会の会長も務めていらっしゃいます。
山崎 長野県舞台技術者協会には100人くらいが所属しています。われわれのように会社組織でやっている人、フリーランスとして個人でやっている人、ホールに所属している人たちの集まりです。内訳は音響、照明、舞台監督、映像、ピアノの調律師などなど。昭和58年に、長野県県民会館ができたんですけど、上野にある東京文化会館で活躍されていた本田恭二さんが舞台課の課長に就任され、そのときに官と民が交流する団体をつくろうと提案してくださったのが始まりでした。僕は創立メンバーで、会長としては5、6代目になるのかな。

――県内には会社組織でやっているところはどのくらいあるんですか?
山崎 個人でも会社組織で動いている人も加えれば20以上あるんじゃないかな。どうやって会社を維持していくか、という苦労はみんな同じ状況だと思います。というか、日本中が同じ状態。恐ろしいなんてものじゃないですね。うちの場合は週に1日、午前か午後に出社してもらっている以外は自宅待機になっています。会社に来てもやることがない。最初のうちは時間があるから機材のメンテナンスをやろうとか、コードの整備をしようとかやったんだけど、それだって一回やってしまえば終わり。そこから機材がまったく動かないんだから。あとは助成金に頼るしかない。こんなことになるとは思わないから4月に新入社員を5人採用したんですよ。申し訳ない気持ちですよ、入学式をしたきり家に待機している中高生と一緒ですから。
協会で会議を行っても、とりあえず困っている状況を共有するんだけど、最終的にお金が必要ということに行き着くしかない状態。われわれの場合、ホールが開いて、安心して催し物ができるようになって、地元の芸術・文化団体が利用しなければ仕事が生まれてこないんです。
――プロのアーティストの催しを担当される場合もあれば、一般の方の催しをつくり上げることも多いんですよね?
山崎 割合的には一般の方と行う催しが多いですね。一般の方の場合は、ほぼ年に1回の発表会じゃないですか。そのために毎週毎週集まって練習してきて、その成果を披露するわけです。でも集まれない状況になった。結局は中止せざるを得ないわけですよ。たとえ7月から会館が開きますと言われても、すぐには動けませんし、「じゃあ来年にしましょう」となることがほとんど。来年まで会社が健全でいられればいいんですけどね。どうやって社員を解雇しないで給料を払うか、そのことばかり考えていますよ。いかに弱い職種かということを痛切に感じました。できることと言っても蓄えを増やすことしかないんですけど。リーマンショック、阪神淡路大震災、東日本大震災とありましたけど、こんなことは初めてですからね。
――……
山崎 だからって愚痴ってばかりいるわけにもいきません。会社のWebやFacebook、Twitter、YouTubeを駆使して長野舞台として発信していくことも考えているんですよ。音楽であったり、朗読であったり、みなさんを元気づけるものを。それが仕事になるかならないかではなく、長野舞台が頑張って生き残っているんだということの証明にもなるじゃないですか。われわれは受け身の仕事だから、相手から依頼がないと動けない。でも技術はあるから、それをフルに発揮して発信することはできる。
――そこでプロの腕前を見せようと。
山崎 そうだね。実は早くから考えていたんだけど、みんなが簡単に発信できる時代だから逆に様子を見ていたんです。プロがわざわざやる意味を考えていました。だったら当然のように一般の方々とは違うものをつくらないといけない。
われわれの仕事は遊びのように夢中になれる
それが間接的にお客さんを喜ばせられることに、誇りを感じる
――改めて舞台の仕事っていかがですか?
山崎 それはもちろん誇りの持てる仕事ですよ。演出家がいて、物事を決めているからそれに沿ったものにしていかなければいけないけど、いろんな発想を提案できる。言ってみれば遊びの延長なんだと思うんです。遊びのときは日が暮れようが気づかずに夢中になっているでしょ。そのくらい面白いし真剣になれる。しかもそれが間接的に人に喜んでもらえることになるわけだから。
実は僕はもともと役者を目指していたんですよ。東京芸術座に所属していた。村山知義さんがまだお元気なころに。小林多喜二の『蟹工船』に憧れて、この劇団に入ったわけ。大学を目指した1970年は学生運動の最後の年。学校もかなり激しくて、ロックダウンだから授業にならない。デモにも行きました。一番多感な時期がそういうものだったからね。まあ、国や政治がどうのこうのじゃなくて、憧れだけで参加してた。その時期にちょうど劇団員募集があって、授業にならない大学にいるより劇団の方が早いだろうと……。
――その話は初めて伺いました。
山崎 ほとんど話したことがないから。そもそも中学、高校は演劇部だったんだ。中学の国語の先生がシェイクスピアが大好きで、『ヴェニスの商人』『マクベス』をやったし、高校の最後の公演は『リア王』だった。中学の学習の一環で見た映画、ミケランジェロの半生を描いた『華麗なる激情』のおかげで人生観が変わったかもしれない。キリスト教を知ったこと、神の存在を知ることができたこと。労演にも入っていて、そこで『蟹工船』を見たんだけど(おそらく1968年か69年)、強烈だったよね。それが演劇に進んだこと、『蟹工船』にどう結びつくかわからないけど。
――劇団では村山さんに何か教わった記憶は?
山崎 いやあ、遊ぶことだけだね。劇団では座員になったんだけど、たまたま長野に帰ってきたら、親父の友達の紹介で、こういう仕事があるよって言われて連れていかれたところが、この仕事だった。それが22歳で、そのまま今に至るんですよ。
そのころは労音、労演がいちばん盛んだったころ。それでも日本舞踊やバレエ、芸術祭での発表会と一般の人が発表をするときのお手伝いはずいぶんとした。長野市民会館だ。その当時、市民会館に春原さんという舞台の方がいて、その人に舞台人としての心構えや生き方を教わった。それが今の自分の根幹になってる。春原さん、周りからは「ガンさん」と呼ばれ、われわれの業界で「ガンさん」を知らない者はモグリだと言われたくらいの人で、言われた忘れられない言葉がある。「いいか、俺たち裏方は芸術家じゃない、だけどなぁ芸術を理解しようとする心と勉強を忘れるな。それと好きになることだ、好きになれば一生懸命になれる、一生懸命に打ち込めばわかってもらえる、いいな、忘れるなよ!」。それが今の自分の生き方にもなってる気がする。
ホールや会館が街をつくるのではなく、市民がホールや会館を育てる
本当の意味で市民の心の拠り所、憩いの場になっているかが大事


――今回のコロナのことで感じたことを教えてください。
山崎 よく劇場や会館が街をつくるって言うじゃない。でも劇場、会館は街をつくれないと思うんですよ。街に暮らす人びとが劇場や会館をつくっていくものだと思う。県立、都立、国立と言うと遠い存在になってしまうけど、市立などの身近な施設だよね。いかに市民が会館に寄り添っているか。その会館が心の拠り所、憩いの場になっているかが大事なこと。たしかに今回のように行政がストップをかければ止まってしまうんだけど、最終的には市民の皆さんの考え方次第じゃないかって僕は思う。そして、その会館に柔軟な考え方を持ったスタッフがいれば、割と早くオープンできるんじゃないかな。建てるのは行政でも施主は市民、市民の持ち物なんだから。
――市民が会館そのもの、そこで行われている活動に関心を持つことですね。
山崎 そう。と同時に、催し物の裏方を市民だけでやっているところ、市の職員だけでやっているところが結構あるんですよ。そういうところはこの機会に整理してほしい。一つには舞台裏の作業には危険が伴うから。そして何より本物を与えてあげられないでしょ。そうした会館に僕らのような技術者がうまく配置されればいいんだけどね。そういう意味では、僕ら自身も技術スタッフの仕事やその必要性をもっともっと知ってもらう努力をしなければいけないと思う。行けば会館の照明がつくもんだと思っているお客さんも未だに多いから。カラオケだったら明るければいい、マイクの音が出ていればいい、それはつまり別にあってもなくてもいいということになるんだよね。でもそれは僕らの仕事のことを知らないから。NHKの「のど自慢」だって、ゲストが歌うときはちゃんと明かりが変わるんだよ。その意識は子供のころから本物の感動に触れていないとわからないですよね。そうした役割を行政と一緒につくっていくことも必要かもしれない。
われわれは消費者としてでき上がったものでしか評価しないし、目にしない。でもその裏には多くの人手と時間と手間がかかってる。舞台も同じで、演ずる人の裏には多くのスタッフが時間と英知を結集して一つの舞台が成り立っている。そのことをもっともっとアピールしていかなければと痛感する。今回の新型コロナの事態で改めて考えさせられたね。