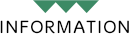[聞く/entre+voir #009] 原 悟さん (信州上田フィルムコミッション マネージャー)〜上田市新風録〜①
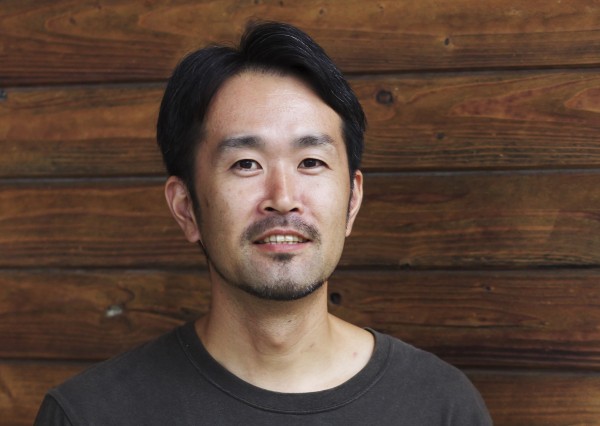
市民一丸で盛り上げてくれるような環境を作るために
地元の皆さんが映画をたくさん観てくれるようにすることも大事。
設立15周年を迎えた信州上田フィルムコミッションのマネージャー・原悟さんへのインタビュー後編です。前編は、上田市と日本映画の関係を聞きましたが、ここでは、フィルムコミッション(以下FC)の仕事について具体的に語っていただきました。話は、“上田映画”の将来のことなどにも及びました。
◉日本で初めてFCが誕生したのは2000年で、歴史はさほど長いものではないですよね。
FCの存在がクローズアップされたのはたぶん石原慎太郎さんが都知事のころで、自治体の長が「銀座でカーチェイスをしたい」とか、行政が撮影に関与するような発言をされたことが最初のような気がします。そのころからFCの研究が盛んになり、2000年に大阪で初めて立ち上げられました。多くが政令指定都市の中で、人口わずか12万人ほどの上田市が10番目に手を挙げました。上田はすでに長いロケ支援の歴史があったので、看板を掲げるだけでスタートできたのだと思います。
◉原さんはFCに関わられて、何年になるんでしょうか?
14年目です。最初はやりたくて始めたわけじゃないんですよ。日本中探してもFCをやりたくてやっている人というのはそれほどいないんじゃないでしょうか ? きっと役所の異動などでめぐりめぐって「お前やれ」みたいなケースが多いんじゃないかな(苦笑)。僕の場合も東京で働いていくんだろうと漠然と思っていた矢先にたまたま声がかかったんです。当時の上田市役所の観光課長でFCの母体となる上田観光コンベンション協会の事務局長が僕の父親の同級生でした。それで「東京になんかいないで帰ってきてFCをやらないか」と言われたんです。映画は好きだったけれど単に観客でしかなかったから、実際にどうやって作っているのかとかそんな専門的なことは一切わからないまま、またそもそもFCというものが一体なんなのかわからないままに始めることになりました。それで引き受けてしまう僕も僕なんですが…。
僕は今、マネージャーという立場ですが、当時のマネージャーだった小林純行さんは、東京で広告のプランナーなどをやっていた方で映像のことも詳しかった。私にとってはこの人に出会えたのが非常に大きく、すべてをこの人から教わったといっても過言ではないと思います。芸術家肌の兄貴分で、私の目標であり尊敬する人でもあるけれど、反面教師でもあり、それはとても愉快な人でした。小林さんはFCの世界でも有名で、現ジャパン・フィルムコミッションの前身に当たる全国フィルムコミッション連絡協議会の時代から、中央でもFCの人材育成や映像産業の振興などに寄与してきました。文化庁の文化芸術振興費補助金の審査員や、釜山国際映画祭ではゲストスピーカーとして招かれたこともありました。けれど、信州上田フィルムコミッションがちょうど10年目に入った時、ロケ中に体調を崩しその後約1年間の闘病生活を経て亡くなられてしまいました。
◉そこから原さんが前面に立ってやってこられたわけですね。ものすごい大所帯のロケ隊を、段取りよく動かさないといけないわけですよね。当初はいかがでしたか?
そうですね。FCに入ったころは本当に面食らいました。1年間を通して「1対100」みたい状態が切れ目なく続いていくんです。たまにロケ隊に顔見知りの方が混じっていることもありましたが、僕は人見知りだったので、とにかくつらくて、つらくて。まったく皆さんの顔と名前が覚えられませんでしたね。
初めての出勤の日に、小林さんから「あのロケバスに乗れ」と言われて、どうしていいのかわからないままロケ現場に行ったんです。現場でも何をしていいかもわからないし、とりあえず飛び交っている言葉を聞いていましたね。専門用語なんかが飛び交うと何を言っているのかまったくわかりませんでした。終いにはエキストラの人が怒り出して帰ってしまったもんですから、「どうなってんだ」と怒号が飛び交い始めたので「俺がやります!」って。仕事はそうやってバタバタしながら現場で覚えていきました。入った年が一番忙しくて、本当に1年を通して3、4日しか休みがありませんでした。朝3、4時まで撮影して6時には次の現場に行くみたいな。今は年間に50〜60作品ですが、当時は110作品くらいありましたね。しかも撮影だけではなく、上田の場合は、撮影から宣伝まで、つまり入口から出口まで全部関わっていきます。1年間みっちりやれば、すべて身に付きますよ(笑)。最初の2年間は死にもの狂いでしたが、おかげで彼らが何を求めているのか、どういうところを掻いてやれば喜ぶのかがよくわかるようになりました。
◉今おっしゃった「最初から最後まで」というのは何を指しているんですか?
上田ではこれまでたくさんの映画が撮られてきました。でも実は、全国津々浦々さまざまな街に化けてきたけれど、上田が舞台になることってほぼなかったんです。これからは、できるだけそうしたこれまで上田になかった作品もやっていきたいと思い、懇意にしているプロデューサーさんなどに企画相談したりもしています。こちらから提案した作品ではないけれど、昨年は『サムライフ』という作品で、上田で起こった実話をすべて上田で撮影するという悲願をたくさんの皆さんの協力の中で実現することができました。来年以降も、少しずつこうした上田ありきの企画作品を発表できると思うので楽しみにしていて下さい。きっと喜んでもらえるだろうし、早く言いたくて仕方ないんですが、なんだかんだあれこれもう3年近く準備してきているのでもうちょっと我慢したいと思います。でも、もちろん毎年やれるような甘いものではないので、それこそじっくりと。今までやってきたオーダーに応えるという仕事の裏で、1本1本ゆっくり進められたらいいなと思っています。
今お話ししたのが入口です。要するに企画の部分ですね。出口の方はというと、その逆で作品が完成してそれをより多くのお客さんに届けていく所、配給・宣伝の部分です。公開が決まっても多くのFCでは「どこどこで撮りました」とPRするくらいで、劇場動員の後押しにつながるような取り組みはあまりやらないんですよ。察するに「ここは興行だから、行政があまり絡みたくない」とか「制作は制作、公開は公開」ということがあるのかもしれません。うちはそこは後押ししていかなきゃなと思っているんです。FCのミッションのひとつに、映像作品を通じた観光誘客がありますが、興行収入1億円の作品と10億円の作品とでは、当然10億円の作品の方が観光への可能性が膨らむと思うんです。
◉その通りだと思います!
『サマーウォーズ』(2009年)のときに気づいたんですが、うまくいくときって、僕ら関係者だけが動くのではなく、「私たちにも何かできることはありませんか」などと一般の方からも共に盛り上げたいとご相談を頂くことが多いんです。それは試写を観て自分たちの街がロケ先になっている喜びもあるのだと思いますが、『サマーウォーズ』の場合は街に暮らす方々にとっても心熱くなる作品だったからこそ、その魅力を発信したいと思って頂けたのだと思っています。だからこの時、僕は権利処理だとかアドバイスをするだけでよかった。その結果すごく広がりが出て、興行収入は目標の1億円を超えて13.5億にまで跳ねました。公開から5、6年たった今でもまだファンが舞台となった上田にいらしてくれるのは、この時に市民一丸で盛り上げてくれたおかげだと思っています。感動した生の声、純粋に応援したいという空気感のおかげで盛り上がった。そういう映画を作るためには地元の人が観る環境を整えていかないといけない。そのための取り組みだけはしようと思っているんです。
『青天の霹靂』(2014年)の場合は、全国300スクリーンでの公開で、劇場別の興行成績は、首位の大阪・梅田の映画館に次いでTOHOシネマズ上田が全国2位となりました。大都市と肩を並べ、こんな小さな街の映画館が日本全国のどこよりもお客さんを集めたのです。昨年の『おかあさんの木』(2015年)は上田ロケ作品ではないものの、原作者が上田市に隣接する坂城町出身で上田高校卒業生の児童文学者・大川悦生さんだったんです。それから地元が舞台になった作品でしたので、戦後70周年に、戦争を知らないこどもたちが地元の原作者が描いた物語で、かつ、地元を舞台に撮影された作品で学習できる非常にいい機会ではないかと、大展開しました。これは劇場別の興行収入で上田が全国4位だったんですが、東日本では僅差の2位でした。ロケ作品でもない作品がこれだけの成績を上げられたことは大変自信にもなりましたし、同時に大きな手応えも感じました。上田にゆかりのある作品を上田の人が以前にも増して観てくれるようになってきていることを僕はとてもうれしく思います。このことは観光であれ何であれ映画で何かコトを起こそうとした時にすごく大きな力になってくれると思っています。
◉上田の方は特別に映画好きだったりするんですか(笑)?
ははは! それはほかの街と比べようがないですね(笑)。でも、上田の街のあらゆる所で人がしゃべっていることに耳を傾けてみると、「大泉洋が行ったとかっていうあの店行ったか? 行列で入れねえぞ」とか、「あの角に交番なかったっけか?」(セットのこと)とか、「定年退職してから暇でエキストラするくらいしかやることねえぞ」とか、映画・映像に関連した何らかの話が聞こえてくる。そのことに気付いた時、すごくうれしくて、映画が街に根づいている感じがすごくいいなあと思いました。そういうのが日常の風景になってずっと続いていったらいいなあ、素敵だなあと思っています。
◉これまでの体験のなかで一番つらかったこと、うれしかったことはなんでしょう?
つらかったことは、『ラストゲーム 最後の早慶戦』(2008年)で、毎週各土日400人のエキストラさんをひと月集め続けたことです。これは吐きそうなくらい大変でした(苦笑)。せっかく集めた人たちも、雨が降ったことで全員バラす(断る)はめになったり…。また大河ドラマ『真田丸』では、地元でロケをしてほしいものの、残念ながら市内にこの時代設定に耐えられる場所はほとんど残っていないことがきつかったですね。場所はないが誘致することが至上命題だったので、いつもならあきらめちゃうんだけどこのときばかりは林道マップを片手に何カ月にもわたって山という山、行ったことのない林道をすべて走破する勢いでした。
うれしかったのは市川崑監督の『犬神家の一族』(2006年)かな。巨匠とご一緒できた最初で最後の機会でした。とにかく犬神家設定のロケ場所を探すのが大変でした。市川監督は望遠レンズを使うんです。それが監督の画作りの特徴で、それによりすごくパリッとした、ピシッとした絵面になるんです。最初の殺人が起こって菊人形の首が人間の首にすげ変わっているシーンですが、金田一耕助が疾走してくる姿を望遠レンズで撮るということで、建物に雰囲気があることはもちろん、カメラの引きじりをとりつつそれでいて横移動もできる場所を探さなければいけなかった。市川監督は私みたいな小僧にそうそう話しかけてくれるような人ではなかったのですが、このときばかりは「いい場所だ」とほめてくださったんです。それがとてもうれしかったですね。
結局このロケには毎日帯同しました。毎日いろんなことが起こりました。例えば曇りじゃないと撮らないんです。晴れすぎていると撮らない(笑)。それだけだったらまだいいんです。柳町という古い通りを金田一が走り抜けるんですけど、路面が石畳になってしまっていたから、撮影日に朝から通行止めにして100メートル近い範囲に砂をまいたんです。でも晴れてしまったから…結局中止になって全部回収しました。そうこうしているうちに、今度は大屋駅に行こうということになったんです。大屋駅での撮影の段取りとしては、白いガードレールみたいな網があるんですけど、撮影日に木の柵に差し替えるという手はずになっていました。でもそれを撮影日ではない今日、しかも鉄道会社のお休みの日に今すぐそれをやることに。鉄道会社の担当の方にもお休みのところわざわざ出てきてもらって、どたばたでしたね。当時の吉村専務(東映テレビのプロデューサー)から、これは後々語れるロケになるからよく見ておくようにって言われたものです。そしてこのロケを通じて、物事はなんとかなっちゃうもんなんだな、というのを学びましたね(笑)。
◉そういう環境から、鶴岡慧子さんのような若い才能が誕生したことが素晴らしいですね。
そういう意味では“今”に興味はなくて、もっと長期的に考えていますね。たとえば鶴岡慧子という監督が一人育つことで、この先30、40年、楽しみができるわけですから。僕らの仕事は映像を切り口として街に何が還元できるか、できそうか、そのくらいざっくりした中で、じゃあこういうことができるねということがあれば、トライする、しらみつぶしにやっていく、ということでいいのかな、と思っています。だから、街をつくっていくのは人だから、長期的には人が育つのがいちばん。それを映像を通して何らかのきっかけをつくれればいい。街の人が映画で育つとか、豊かになっていくとか、そういったことに挑戦できるのがこの仕事のやり甲斐ですね。
◉改めて、原さんの思いを聞かせてください。
この街が抱えている映画の歴史を知ってもらうこと、受け継ぎ、未来につなげていくこと、それが第一の目標です。「90年以上にもわたる映画ロケ支援の歴史」というこの街固有の映画文化を育んできたことが他所のFCとのいちばんの大きな違いですから。私自身としてはこの街の映画文化をもっともっと根付かせていきたいと思っています。観光客が増えるのももちろん嬉しいけれど、上田市の人がいつまでも映画が大好きで大切にしてくれたらもっと嬉しいです。映画と上田市がいつまでも仲良くやっていけるようにその間に入ってチャレンジし続けていきたいと思います。
2016年5月取材
1979年生まれ。長野県上田市出身。
特定地域のロケーションと映像製作者(作品)とをマッチングすることで地域から映像作品を生み出し、
それにより地域活性や文化振興などを試みることを主なミッションとする
フィルムコミッショナーとして、2003年より信州上田フィルムコミッション(以下SUFC)で活動。
これまでに『犬神家の一族』(2006)や『サマーウォーズ』(2009)などを担当した他、
数多くの映画やTVドラマ、CF、MVなど、ありとあらゆる分野の作品制作をサポートしている。
2011年にはSUFCのマネージャーとなり、
『青天の霹靂』(2014)や『おかあさんの⽊』(2015)のタイアッププロモーション、
『サムライフ』(2015)の製作、『過ぐる日のやまねこ』(2015)の
資金調達から配給宣伝のサポートまで、これまで以上に幅広い支援活動を展開している。
また、2015年には「クレイアニメーションワークショップ」を、2016年には「こども映画教室」を開催するなど、
次世代の文化を担う子供たちの育成にも力を入れるほか、市内の老舗映画館「上田映劇」を舞台に2006年から4年間
シアターアコースティックフェス「FUMFAM(ファムファム)」をオーガナイズするなど、
地域の文化活動にも取り組んでいる。
SUFCとしてこれまでに「信州ブランドアワード2011」にて「県知事賞」を、
2015年には第1回「JFC アウォード」で「優秀賞」を受賞した。